実は、私はずーっと営業。次はどこで働こうか…というときに「そうだ!税理士事務所に勤めよう!」と思ったのは、働く中で、どれほど税金(所得税・住民税・社会保険料)が取られているのか…を実感したから・・・というのも一つの理由です。
というのも、最初に勤めていた会社をやめた後、住民税の普通徴収が自宅に届きました。
その額45万円…
今までこんなに高額な税金を払っていたの!?とびっくりしました。
給料から天引をされていると、税金を納めている…という実感がいまいち分かっていなかったのですが、その時にやっと「税金」というものについて興味が湧いたとも言えます。
そのとき20代中盤。
それから10年以上のときを経てサラリーマンでもできる節税方法を実体験と、税の基礎知識をお伝えしたいと思います!
第1章:手取りと天引きを知ろう!!
1.1 サラリーマンでもできる節税・社会保険対策とは
「節税」と聞くと、自営業者や会社経営者だけの特権のように思われがちですが、実はサラリーマン(給与所得者)でも活用できる節税・社会保険料対策は意外と多く存在します。給与明細を見るたびに「手取りが少ない」と感じている方にとって、税金や社会保険料の仕組みを正しく理解し、活用できる制度を賢く使うことは、手取りを増やすための第一歩です。
このコラムでは、「知らないと損をする」サラリーマンのための節税・社会保険料対策について、分かりやすく、実践的に紹介していきます。
1.2 「手取り」を構成する要素を理解しよう
毎月の給与から差し引かれている項目は大きく分けて2種類、「税金」と「社会保険料」です。
- 税金: 所得税と住民税が対象です。年収や家族構成などによって変動します。
- 社会保険料: 健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険など。会社と本人が負担を分け合っていますが、本人負担も無視できない金額です。
また、税金や社会保険料の多くは「年収」に連動して決まるため、年収の調整や非課税制度の活用などによって、合法的に手取り額を増やす余地が生まれます。
本コラムでは、以下の章で詳しく制度やテクニックを紹介していきますが、まずは「自分の収入からどれだけ税金・社会保険料が引かれているのか」「どの制度を活用できるのか」という意識を持つことが重要です。
第2章:税金の節約術(所得税・住民税対策)
2.1 税金の仕組みを知れば、節税が見えてくる
「節税」とは単に支払いを減らすことではなく、法律に則って、正しく税負担を軽減する行動のことです。そのためには、まず税金がどのように計算されているかを理解することが大切です。
給与所得者にかかる主な税金は、「所得税」と「住民税」です。これらの税金は以下の流れで決まります:
1. 年収(給与収入)から「給与所得控除」を差し引いて「給与所得」を算出
→ 給与所得控除は、収入額に応じて自動的に決まります。
2. 給与所得から「所得控除」を差し引いて「課税所得」を算出
→ 基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除などが該当。
3. 課税所得に対して税率をかけて「所得税」を計算
→ 所得税は「超過累進課税」で、所得が高いほど税率が上がります。
4. 住民税は課税所得に対して一律10%程度(自治体によって若干異なる)
このように、税金の多くは「課税所得」をベースに計算されるため、節税の基本は**「所得控除を増やす」こと**にあります。控除を増やせば課税対象が減り、結果として税金も下がるのです。
2.2 控除の活用こそサラリーマンの節税の鍵
サラリーマンにとって最も現実的かつ合法的に税金を減らす方法は、「所得控除」の適切な活用です。控除は種類ごとに条件が異なるため、それぞれの制度を正しく理解し、自分に当てはまるものを漏れなく申請することが重要です。
次章では、具体的な所得控除の種類と、その効果的な活用法について詳しく解説していきます。
2.3 「所得控除」と「税額控除」の違いを理解しよう
節税を考える上で大切なのが、「所得控除」と「税額控除」という2種類の控除制度の違いを知ることです。どちらも税金を軽減する制度ですが、その仕組みと効果は異なります。
■ 所得控除とは
所得控除は、「課税所得」を減らす働きを持ちます。課税所得が減ることで、結果的に所得税や住民税の額も減少します。
例:年収500万円の人が30万円の所得控除を受けると、課税対象となる所得が470万円になります。
税率が20%なら、単純計算で6万円の税金が軽減されます。
主な所得控除の例:
- 基礎控除
- 配偶者控除・扶養控除
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
■ 税額控除とは
税額控除は、計算された税額そのものを直接差し引く制度です。節税効果が非常に高く、対象となる場合は見逃せません。
例:税額が20万円と計算されたあとで、3万円の税額控除があれば、最終的な納税額は17万円になります。
主な税額控除の例:
- 住宅ローン控除
- 配当控除
- 寄附金特別控除(ふるさと納税の一部)
- 配偶者特別控除の一部(条件による)
2.4 所得控除を最大限活用する
所得控除は、サラリーマンが合法的に節税する上での基本中の基本です。ここでは代表的な控除制度と、その活用のポイントを紹介します。
① 基礎控除(全員が対象)
すべての納税者に一律で適用される控除です。2020年以降、所得が2,400万円以下の場合は48万円の基礎控除が受けられます。2025年12月以降に年末調整をしたら58万円以上の基礎控除(所得制限2,350万円以下)になります。
2025年、2026年の2年間限定で、少し基礎控除が増える特例もあります。
所得別で、所得が低い人ほど、基礎控除が高く、全体的に2万円くらい減税される感じです。
② 配偶者控除・扶養控除
家族に所得の少ない配偶者や扶養親族(子どもや親など)がいる場合、その人数や所得に応じて控除を受けることができます。以下の点がポイントです:
- 配偶者控除: 配偶者の年収が103万円以下なら最大38万円(合計所得900万円以下の場合)
- 配偶者特別控除: 配偶者の年収が201万円まで段階的に適用可能
- 扶養控除: 子どもや親などの扶養対象者に応じて適用(子どもが16歳未満の場合は対象外)
③ 生命保険料控除
自分や家族のために支払った生命保険、医療保険、個人年金保険の保険料が対象です。最大で年間12万円(所得控除)まで控除される可能性があります。会社の年末調整で申請が必要なので、保険会社からの「控除証明書」を必ず提出しましょう。
④ 医療費控除
1年間にかかった医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、その超過分を所得控除として申請できます。対象は自分だけでなく、生計を一にする家族全体です。通院や交通費(公共交通機関のみ。自家用車不可)も一部対象になります。
補足:セルフメディケーション税制も医療費控除の代替制度として利用可能です。
⑤ 社会保険料控除
健康保険、厚生年金、介護保険、国民年金(本人・配偶者・親など)の支払いは全額控除の対象です。給与天引き分は自動的に適用されますが、追加で支払った国民年金などがある場合は、別途申告が必要です。
⑥ 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
個人型確定拠出年金(iDeCo)への掛金は全額所得控除されます。サラリーマンでも月額12,000〜23,000円まで拠出でき、老後資金を作りながら節税もできる優れた制度です。
2.5 ふるさと納税を使った実質2,000円の寄附金控除
「ふるさと納税」は、自治体に寄附をすることで、所得税と住民税から控除が受けられ、実質2,000円の自己負担で地域の特産品などを受け取れる制度です。節税しながらお得に地方を応援できる、非常に人気のある制度です。ふるさと納税については「はじめてのふるさと納税|やり方をわかりやすく解説」を御覧ください。
■ 仕組みの概要
- 自治体に寄附する(複数OK)
- 寄附額から2,000円を差し引いた額が、所得税・住民税から控除される
- 控除上限額は年収や家族構成により異なる
- 「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告不要(5自治体まで)
■ 控除の種類
- 所得税:翌年の確定申告時に控除
- 住民税:翌年度の住民税から減額
■ 節税の効果
例えば、年収500万円・扶養1人の会社員なら、年間約6万円までの寄附が可能で、自己負担は2,000円のみ。税金が約5万8千円分控除されることになります。
ふるさと納税をもっと知ろう!!
ふるさと納税を始めたい!詳しく知りたい!という方は「はじめてのふるさと納税|やり方をくわしく解説」を御覧ください。
ふるさと納税の経験者や「いや、でも、地元への納税もしたいけど、節税もしたいんだよね…」という方には「ふるさと納税、ワンストップ特例と確定申告どっち?あなたに合った選び方」を御覧ください。
2.6 NISA(少額投資非課税制度)で資産運用しながら非課税に
「NISA(ニーサ)」とは、株式や投資信託などの運用益が一定額まで非課税になる制度です。2024年から新しい制度に切り替わり、より使いやすくなりました。サラリーマンにとっても、将来の資産形成+節税の手段として注目されています。
■ 新NISAのポイント(2024年~)
- つみたて投資枠:年120万円まで(積立型投資信託に限定)
- 成長投資枠:年240万円まで(個別株やETFも可)
- 生涯投資枠:合計1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
- 運用益(売却益・配当)が完全非課税
- 非課税期間が無期限化され、長期運用が可能に
■ 節税メリット
通常、株式や投資信託の利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で運用すればこの税金が一切かかりません。例えば、10万円の利益が出た場合、通常は約2万円の税金がかかるところが、NISAなら全額手元に残ります。
■ 注意点
NISAは「所得控除」ではなく「非課税運用」の制度です。つまり、今すぐ手取りが増えるわけではありませんが、長期的には大きな節税効果がある制度です。つみたてNISAは初心者向けにも設計されているので、まずは少額から始めるのも良い選択です。
2.7 iDeCo(個人型確定拠出年金)で将来の備えと節税を同時に
iDeCo(イデコ)は、自分で年金資金を積み立てながら、掛金が全額所得控除になるという強力な節税メリットを持つ制度です。特に中長期での運用を考えるサラリーマンにとって、節税と老後資金準備を同時に進められる非常に有効な手段です。
iDeCoについては「iDeCoの基礎を知ろう!!」を御覧ください。
■ iDeCoの基本的な仕組み
- 自分で金融機関を通じて口座を開設し、月額5,000円から掛金を拠出
- 拠出したお金は、株式・債券・投資信託などで運用可能
- 60歳まで引き出し不可(原則)
- 拠出した掛金は全額所得控除の対象となる
■ 掛金の上限(月額)
サラリーマンの場合、勤務先の年金制度によって異なりますが、主に以下のいずれかです:
| 勤務先の年金制度 | 掛金上限(月額) |
|---|---|
| 企業年金なし | 23,000円 |
| 確定給付企業年金あり | 12,000円 |
■ 節税効果の例
年収500万円の会社員が月23,000円、年間276,000円を拠出した場合:
- 所得税率20%、住民税10%とすると、年間約82,800円の節税効果(276,000円 × 約30%)
- 節税は毎年継続されるため、10年間で80万円以上の税負担軽減にもなります
■ その他の節税ポイント
- iDeCoで得た運用益も非課税(通常は約20%課税)
- 受取時にも一定の退職所得控除や公的年金控除が適用される
■ 注意点
- 原則として60歳まで引き出せない(途中解約は不可)
- 資金の流動性が低いので、生活資金とのバランスに注意
- 運用商品選びと手数料の確認が重要
2.8 一時所得の対象となるものも上手に活用する
一時所得は「臨時収入」や「たなぼた系の収入」がです。営利目的ではないもので、継続的でもないものが当てはまります。1年間に50万円までなら控除内なので税金がかかりません。
一時所得の対象となるもの
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるもの以外)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受け取る報労金等
- 資産の移転等の費用に充てるため受け取った交付金の中で交付目的の支出に使われなかったもの
- ふるさと納税で得られる返礼品
ふるさと納税をしている人は、ふるさと納税の返礼品は一時所得に含まれます。
生命保険は死亡保険金、満期解約、一部解約ですべて税金の種類が変わりますが、一時所得にあたるの一部解約です。生命保険の場合、受け取り方(死亡保険金など)と関係者(契約者、支払った人、受け取る人)でもかかる税金(相続税、贈与税、一時所得など)が異なります。
私は生命保険を上手に活用するのもオススメしております♪
第3章:社会保険料の負担軽減策
3.1 社会保険料の仕組みと手取りへの影響
給与明細を見て「所得税より社会保険料の方が高い」と感じたことはありませんか? 実際、多くのサラリーマンにとって、社会保険料は所得税・住民税よりも重い負担となっています。
社会保険料は以下の構成から成り立ちます:
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険料 | 医療費の自己負担軽減や出産手当等の保障 |
| 厚生年金保険料 | 将来の年金給付 |
| 雇用保険料 | 失業保険や育児休業給付などの財源 |
| 介護保険料 | 40歳以上の加入者が対象 |
■ 保険料の計算方法
社会保険料は「標準報酬月額」に基づいて決まります。この額は毎年4〜6月の給与(残業代・手当含む)の平均をもとに計算され、9月から1年間適用されます。
→ つまり、4〜6月の給与が多ければ、1年間の保険料が上がるのです。
→ また、ボーナスには「標準賞与額」に基づいて別途保険料がかかります。
3.2 年収調整で社会保険料を最適化する
上記の仕組みから、ちょっとした工夫で保険料をコントロールすることが可能です。
■ 「4〜6月の残業を減らす」
この期間の給与が社会保険料の基準になるため、残業代が多いと保険料も上がります。可能であればこの3ヶ月だけでも業務調整を検討してみましょう。
■ 「年収を一定の範囲に収める」
社会保険料や住民税の計算には「年収の壁」が存在します。特に以下のラインは注意が必要です:
| 壁のライン | 意味と影響 |
|---|---|
| 106万円の壁 | 社会保険加入義務発生(週20時間超・要件あり) |
| 130万円の壁 | 配偶者の扶養から外れるライン(社会保険料自己負担) |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除の控除額が減少 |
→ 世帯全体での手取りを最適化するには、「扶養に入る・外れる」の戦略的判断が重要です。
3.3 社会保険料を抑える働き方・生活スタイルの工夫
社会保険料は「現金支給された給与」をベースに計算されるため、給与の内訳や働き方を工夫することで、負担を抑えることが可能です。以下は特に実践しやすい方法です。
■ 4〜6月の「通勤手当」を減らす工夫
前述の通り、4〜6月の給与額が「標準報酬月額」の基準となるため、この期間に通勤手当(定期代)を受け取ると保険料が上がる要因になります。以下のような対策が有効です:
- 4〜6月は在宅勤務を中心にする
→ 通勤がなければ通勤手当を支給しない会社もある
→ 会社の制度によりけりだが、交渉の余地あり - 会社の近くに住むことで通勤手当を減らす
→ 距離が短いと定期代も安くなり、標準報酬月額が抑えられる可能性
※ただし、通勤手当が非課税枠(15万円/月まで)内であれば、所得税・住民税には影響なしですが、社会保険料の対象には含まれるため注意が必要です。
■ 在宅勤務手当(テレワーク手当)の非課税化ルール
近年普及した在宅勤務に伴い、多くの企業が「在宅勤務手当」や「テレワーク手当」を導入しています。これには以下のような税務上のルールがあります:
- 在宅勤務にかかる実費相当額は非課税(通信費、電気代など)
- 企業が合理的に算出し、実態に即した額であれば給与とみなされず、所得税も社会保険料も課されない
- 一方で、明確な根拠がない「一律支給型」の手当は、給与扱いとなり課税対象になることも
→ 節税・保険料対策の観点からは、非課税扱いになるよう社内制度を整備してもらうことが望ましいです。
3.4 副業での報酬の受け取り方(業務委託・法人化等)
副業が一般化する中で、その収入が「給与」か「事業所得」かによって、社会保険料や税負担の扱いが大きく異なることをご存知でしょうか。ここでは副業収入の受け取り方によって生じる違いと、節税・社会保険料対策のポイントを解説します。
■ 業務委託契約での収入(事業所得扱い)
副業先と「業務委託契約」を結んで報酬を受け取る場合、その収入は給与所得ではなく事業所得または雑所得となります。これには以下のような特徴があります:
- 社会保険料の対象外(※本業が会社員の場合)
- 必要経費を差し引いた「利益」にのみ所得税が課される
- 青色申告を活用すれば最大65万円の特別控除も可能
→ この方式により、収入が増えても社会保険料は増えず、税金も経費次第で圧縮可能です。
■ 給与扱いでの副業(アルバイトなど)
副業が「給与」として支払われる場合、本業とは別に所得税の源泉徴収や住民税が発生します。また、収入によっては副業先からの報告で勤務先にバレる可能性もあります。
→ 社会保険料への影響はありませんが、税負担の増加に注意が必要です。
■ 副業を法人化する(上級テクニック)
副業収入が安定してきた場合、法人(合同会社など)を設立することで節税・保険料対策が大幅に広がります。
- 会社からの報酬(役員報酬)を調整して社会保険料を最適化
- 法人での経費計上・節税策が多様に使える
- 家族を役員にして所得分散も可能
- NISAやiDeCoなどの制度も併用可能(※重複加入制限に注意)
→ 一方で、法人化には設立費用・維持コスト・事務手続きの煩雑さもあるため、副業年収が500万円を超えてきたタイミングが検討の目安といえます。ひとり社長(マイクロ法人)の場合、税理士報酬は年間でザックリ20万円~です。税理士報酬は売上と、自分で記帳をするか、それも税理士がOK出すレベルで出来てるかどうかで費用は変わってきます。このような必要経費も考慮に入れた上で、法人化をしましょう。
第4章:会社制度・福利厚生を使った手取りUP
4.1 企業型確定拠出年金(企業型DC)の活用
会社が導入している企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が給与の一部を「年金掛金」として積み立てる制度です。
■ 節税ポイント
- 掛金は給与として受け取るよりも社会保険料・所得税が軽減される
- 運用益も非課税で、将来の資産形成にもつながる
- 一部企業では「マッチング拠出(自己追加)」も可能で、iDeCoとの併用が制限される場合あり
→ 給与として受け取って課税されるよりも、年金として積み立てた方が手取りベースでは有利になるケースが多くなります。
4.2 非課税となる会社の手当制度を活用
給与と違い、一定の手当は非課税扱いとされるため、会社制度を活用すれば手取りが増えることにつながります。
■ 非課税となる代表的な手当
- 通勤手当:月15万円まで非課税(ただし社会保険料には含まれる)
- 出張旅費・日当:業務に必要な実費や基準額以内なら非課税
- 在宅勤務手当:合理的に算出された実費分は非課税
- 社宅制度:一定条件下での家賃補助が非課税扱いに
→ 給与として受け取るよりも、「福利厚生費」や「手当」として受け取る方が税負担が軽いケースが多いため、制度の内容をしっかり確認しましょう。
4.3 持株会・ストックオプションの税務メリット
企業によっては、自社の株式を社員が購入できる従業員持株会やストックオプション制度を導入している場合があります。
■ メリット
- 持株会では「奨励金」が非課税で支給される場合あり
- ストックオプションは、権利行使時・売却時の利益に対し**分離課税(20%)**が適用され、通常の給与所得より低税率になるケースも
→ 長期的な資産形成+節税という観点でも活用の価値がある制度です。
4.4 教育・資格取得・福利厚生補助
会社が提供する教育制度や資格取得支援、福利厚生サービスも実は「課税されない支出」として見逃せません。
- 資格取得費用補助(会社負担なら非課税)
- 社員研修・通信教育(自己啓発を目的とする場合)
- 福利厚生費としての保養所利用、レジャー補助など
→ 自費で支出するよりも、会社制度を通じて受ける方が税務上お得になります。
第5章:人生イベント別の節税対策
5.1 結婚・出産・育児にまつわる控除と給付
ライフステージの変化に応じて、所得税や社会保険料の負担が変わるだけでなく、さまざまな控除や給付金制度を活用するチャンスが生まれます。
■ 結婚した場合
- 配偶者の所得が一定以下なら配偶者控除・配偶者特別控除が適用可能
■ 出産した場合
- 出産育児一時金:原則50万円(健康保険より支給)
- 医療費控除:出産費用は対象(保険金等との差額)
- 育児休業中の社会保険料免除:給与がなくても保険加入継続&将来の年金に影響なし
出産に関する税金や給付については「産休・育休に入る前に知っておきたい!お金と制度の基礎知識ガイド」を御覧ください
■ 育児期のポイント
- 児童手当(月1万〜1.5万円)
- 0~15歳までは扶養控除はない!扶養控除ができるのは16歳~
「え!!子どもに扶養控除がないなんて嘘だろ!?」と思う方は「【年少扶養控除の歴史】廃止と児童手当の関係!復活したらどうなる?」を御覧ください。
5.2 住宅購入と住宅ローン控除
住宅を購入した場合、最大13年間にわたる住宅ローン控除が受けられる可能性があります。これはサラリーマンにとって非常に大きな節税効果をもたらす制度です。
■ 控除の概要(2024年以降)
- 年末時点の住宅ローン残高×0.7%を所得税から控除(上限あり)
- 所得税で控除しきれなかった分は翌年度の住民税から控除可能(最大13.65万円)
■ 控除対象の条件
- 合計所得2,000万円以下
- 新築・省エネ基準を満たすこと(中古住宅にも要件あり)
- 借入期間が10年以上 など
→ 控除額が大きいため、確定申告を忘れずに行うことが重要です(初年度のみ申告必要、以降は年末調整可)。
5.3 介護・相続・贈与に関する節税視点
高齢の親の介護や、相続・贈与といった場面でも、制度を活用することで負担を大きく軽減できます。
■ 介護が必要な場合
- 医療費控除の対象になる場合がある(訪問看護・施設費用など)
- 特定疾病にかかる治療費や、障害者控除の対象になるケースも
■ 相続・贈与への備え
- 年間110万円までは贈与税がかからない(暦年課税)
- 教育資金の一括贈与や住宅取得資金の贈与など、特例を使えば非課税枠が拡大
- 相続対策として生命保険や不動産の活用も有効(遺産分割・非課税枠の利用)
→ 相続・贈与は早めの準備が節税の鍵。専門家に相談するのも選択肢です。
第6章:注意点と節税の落とし穴
6.1 節税のつもりが脱税に…?違法と合法の境界線
節税と脱税の違いは、「法律の範囲内かどうか」にあります。正当な手続きを経て税負担を軽減するのは節税ですが、以下のような行為は脱税・申告漏れとして指摘される可能性があります。
- 架空の経費を計上して所得を減らす
- 副業収入を申告せず放置する(会社バレ回避のつもりがリスクに)
- 不動産や仮想通貨の売却益を確定申告しない
→ 悪意がなくても、「知らなかった」では済まされないのが税務の世界です。グレーな節税方法に手を出さないよう注意しましょう。
6.2 安易な節税商品に注意
「節税になる」と勧められる保険や不動産投資なども、必ずしも効果的とは限りません。特に以下のような商品には要注意です。
- 節税保険(法人向け保険など):制度変更によりメリットが消えるケースあり
- アパート・マンション投資:減価償却での節税効果は一時的、空室リスクも
- 仮想通貨節税スキーム:法改正や計算ミスによる課税リスクが高い
→ 節税目的だけで商品を選ぶと、本来の目的(資産形成や保障)が損なわれる恐れがあります。節税「効果」だけでなく、「本質的な必要性」と「リスク」を見極めることが重要です。
6.3 制度改正に常に注意を
税制は毎年見直しが行われます。最近では以下のような変更がありました
- 新NISA制度(2024年〜)の開始と非課税枠の大幅拡大
- 住宅ローン控除の見直し(省エネ基準の強化)
- 配偶者控除や扶養控除の適用要件の厳格化
- 基礎控除の拡大&所得別
→ 過去に使えた制度が、今年から使えない可能性もあるため、制度の変化をチェックし続けることが大切です。毎年の年末調整や確定申告の際に、最新情報を確認しましょう。なお、税制改正は毎年12月15日前後に発表されます。税制改正は「こんな感じに変えるよ!」という予告と思って下さい。
第7章:まとめ
7.1 サラリーマンが今日からできる手取り改善アクション
本コラムでは、サラリーマンでもできる節税・社会保険料対策を網羅的に紹介してきました。ここで改めて、今すぐ始められる具体的なアクションをまとめます。
■ 所得税・住民税の対策
- 控除を最大限活用する(生命保険・医療費・扶養控除など)
- iDeCoで老後資金+所得控除
- ふるさと納税でお得に地域応援&節税
- NISAで非課税運用を開始
- 確定申告で過払い税金を取り戻す
■ 社会保険料の見直し
- 4〜6月の給与・手当を意識して保険料を抑える
- 通勤手当を調整・在宅勤務を活用
- 副業の受け取り方を工夫(業務委託・法人化)
- 配偶者や家族の年収調整で世帯全体の手取り最適化
■ 会社制度を使い倒す
- 福利厚生・非課税手当を最大限活用
- 企業型DCや持株会などの制度に注目
- 教育・資格取得補助も「非課税メリット」がある
■ ライフイベントを節税チャンスに変える
- 結婚・出産・育児・住宅購入・介護など、節目ごとに活用できる制度を確認
- タイミングを逃さず申請・確定申告を忘れずに
7.2 情報収集と専門家の活用も選択肢に
税金・社会保険の制度は年々複雑化・変化しています。すべてを自力で完璧にこなすのは難しくても、「知っているかどうか」だけで数万円〜数十万円の差が生まれることもあります。
- 国税庁や市区町村の公式サイトを定期的にチェック
- 節税に詳しい税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)への相談も視野に
- 年末調整・確定申告のタイミングで見直すクセをつける
- 当サイト「わかる税」は非経営者の一般的な方に向けて作っているサイトです!ぜひ、ブックマークなどで定期的に見にいらしてくださいませ♪
最後に
サラリーマンでも、節税・社会保険料対策を通じて合法的に「手取りを増やす」ことは可能です。難しそうに見える制度も、一つひとつ丁寧に確認し、自分に合ったものを選ぶことで、確実に家計にメリットをもたらします。
今日からできることを一つずつ実践して、将来に備えながら、賢くお金を守りましょう。
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 暮らしと税2025年7月17日サラリーマンができる節税・社会保険対策 〜手取りを増やすための実践ガイド〜【初心者向け】
暮らしと税2025年7月17日サラリーマンができる節税・社会保険対策 〜手取りを増やすための実践ガイド〜【初心者向け】 副業と確定申告2025年7月15日ウッカリ2度税金を払ったらどうなる?返却は自己申告必要?
副業と確定申告2025年7月15日ウッカリ2度税金を払ったらどうなる?返却は自己申告必要? 雑談2025年7月15日わくわく広場 四谷三丁目店にお邪魔してみた!
雑談2025年7月15日わくわく広場 四谷三丁目店にお邪魔してみた!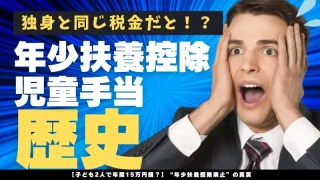 暮らしと税2025年7月14日【年少扶養控除の歴史】廃止と児童手当の関係!復活したらどうなる?
暮らしと税2025年7月14日【年少扶養控除の歴史】廃止と児童手当の関係!復活したらどうなる?

