選挙が近いせいか、年少扶養控除が話題になっていますね。
子育てしている身としても、税コラムニスト(?)としてもとても嬉しく思います。
ですが、SNS等を眺めていると、まだまだご理解頂けていないのだなぁと感じる部分もあります。
年少扶養控除については「年少扶養控除は今はない!もしも復活するなら【N分N乗?扶養控除増額?】」「にて語っているので、今回は本来なら全員にあるはずの人的控除についてを語りたいと思います。
第1章:人的控除ってなに?
◆ 税金が安くなる「家族への配慮」の制度
所得税や住民税には、「所得控除(しょとくこうじょ)」という仕組みがあります。これは、収入があっても、すべてが課税対象になるわけではなく、生活に必要な一定額を差し引いて税金を計算してくれる制度です。
その中でも「人的控除(じんてきこうじょ)」は、家族構成や個人の事情に応じて税金が軽くなるしくみ。たとえば、配偶者や子ども、親などを扶養している場合、税金が安くなるのはこの人的控除のおかげです。
これは国が「家族を支えている人には税金の負担を少し軽くしましょう」という考えに基づいて作られた制度です。
◆ 所得控除の中の“ひとつのカテゴリ”
人的控除は、所得控除の中でも「人」に関する事情を理由とした控除です。たとえば、以下のような控除が含まれます:
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除 など
これらはすべて「その人や家族の状況」に配慮した控除であり、まとめて「人的控除」と呼ばれます。
◆ 控除があると、どれだけ税金が減るのか?
所得控除は「課税される金額(課税所得)」を減らすしくみなので、実際に減る税金は人によって違います。
たとえば、所得税の税率は5%~45%の間で変わりますが、
- 控除額が38万円
- 税率が10%
という人なら、38万円 × 10% = 3万8千円 税金が軽くなるという計算になります。
◆ 控除を受けるには?
多くの人的控除は、年末調整や確定申告で申告することで受けられます。何もしなくても自動的に適用されるわけではないので、注意が必要です。
- サラリーマンの方は「扶養控除等申告書」などの提出でOK
- 自営業の方は確定申告で申請
家族構成に変更があった年(結婚、離婚、出産、親の同居など)は特に気をつけましょう。
第2章:基礎控除 - すべての人が対象になる“スタートラインの控除”
◆ 基礎控除ってなに?国が認めた「最低限の生活には税金をかけない」ルール
基礎控除とは、すべての納税者が無条件で受けられる所得控除で、所得税・住民税の計算において、まず最初に差し引かれる「スタートラインの控除」です。
では、なぜこんな制度があるのでしょうか?
その背景には、日本国憲法 第25条の理念があります。
第25条〔生存権〕
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
この条文の趣旨に基づき、税制においても「最低限度の生活に必要な部分には課税しない」という考えが採用されています。
それが形となったのが「基礎控除」なのです。
つまり、「あなたが生活していくうえで最低限必要な金額には税金をかけませんよ」という、国の保障に基づいた控除なのです。この後に語る、配偶者控除、扶養控除なども、すべて生存権由来の控除です。
◆ 令和7年からの改正:年収が少ない人ほど控除が増える!
昔はすべての人が一律で控除がありましたが、2020年から所得制限ができ、48万円の控除(合計所得2,400万円以下の場合)を受けられました。
しかし、令和7年(2025年)から2年間限定で、年収が少ない人ほど控除額が大きくなる特例措置が導入されました。
これにより、所得税がかからない「非課税ライン」も大きく引き上げられました。
◆ 【最新版】基礎控除額 早見表(所得税)
| 合計所得金額(給与収入目安) | 令和7・8年(特例有) | 令和9年以降(通常) |
|---|---|---|
| ~132万円(給与約~200万円) | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超~336万円(給与約200~475万円) | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超~489万円(給与約475~665万円) | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超~655万円(給与約665~850万円) | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超~2,350万円(給与約850~2,545万円) | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超~2,400万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
◆ 「160万円の壁」ってなに?
この新しい基礎控除制度により、所得税がかからない収入の上限が160万円になりました(従来は103万円)。
なぜなら…
- 基礎控除:最大95万円
- 給与所得控除:65万円(年収162.5万円以下なら一律)
この合計で160万円までの収入なら所得税がかからないことになるのです。
「103万円の壁」と言われていた時代から一歩進んだ、新しいラインが「160万円の壁」です。
ただし、社会保険料の壁も忘れてはなりません。実際には社会保険料の壁は106万と150万円にあります。
現在は会社規模によって106万か150万かが決まります。人数が50名以下かどうかがポイントなので確認しましょう。
◆ 住民税の基礎控除は?
住民税にも基礎控除がありますが、こちらは原則43万円で、所得に応じて段階的に減額されます
◆ 基礎控除は「最低限の生活保障」だからこそ知っておきたい
- 基礎控除は誰もが受けられる“生活を守る税のバリア”
- 令和7・8年は一時的に最大95万円まで拡大
- 所得税がかからないラインも160万円に引き上げ
- 令和9年からは控除縮小に戻るため、将来設計に注意
第3章:配偶者控除・配偶者特別控除 - 働き方で変わる“夫婦の税金”
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、主に稼いでくる人の合計所得が1,000万円行くかどうかで判断されます!
◆ 「配偶者控除」とは?
配偶者控除は、配偶者(夫や妻)を養っている人の税金を軽くする制度です。
主に「夫が働いて、妻はパート」などのケースで使われることが多いですが、性別に関係なく使える制度です。
◆ 控除が受けられる条件
- 法律上の配偶者であること(内縁関係はNG)
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入だけなら年収103万円以下)
- 自分の合計所得金額が1,000万円以下であること
この条件をすべて満たすと、「配偶者控除」が適用されます。
◆ 控除額は?(所得税の場合)
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額(一般の配偶者) |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超~950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超~1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 0円(対象外) |
※住民税では控除額が異なります(一般的に33万円)
◆ 「配偶者特別控除」とは?
配偶者控除の対象にならない場合でも、配偶者の所得が一定以下であれば、「配偶者特別控除」が使えます。
つまり、「配偶者の収入が103万円を超えたらいきなり『はい、課税!』となるともっと働きたいのに働けない…」というジレンマが生じますよね。それに配慮し“徐々に控除が減るゾーン”に対応した制度です。
◆ 配偶者特別控除の条件
- 配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下
(給与収入だけなら、年収103万円超~201.6万円以下) - 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
◆ 控除額の早見表(ざっくり目安)
| 配偶者の給与収入 | 控除額の目安 |
|---|---|
| ~103万円 | 配偶者控除(38万円)適用 |
| 103万円超~150万円 | 配偶者特別控除(最大38万円) |
| 150万円超~201万円 | 配偶者特別控除(段階的に減少) |
| 201.6万円超 | 控除なし |
※こちらも、納税者本人の所得に応じて控除額は減少します。
◆ 「103万円の壁」「150万円の壁」とは?
- 103万円の壁:配偶者控除が使えなくなるライン
- 150万円の壁:配偶者特別控除が減り始めるライン(満額がもらえる最後の年収)
- 201.6万円の壁:配偶者特別控除も完全になくなるライン
これらの壁は、所得税や住民税の節税、夫の手取りに影響するため、多くの家庭で気になるポイントです。
◆ 注意!社会保険の「106万円・130万円の壁」とは違う話です
配偶者控除の「103万円の壁」は所得税の話ですが、社会保険の扶養には別の壁があります。
| 壁の種類 | 内容 | 主な影響 |
|---|---|---|
| 103万円 | 所得税(配偶者控除) | 夫の税金が安くなるかどうか |
| 130万円 | 社会保険の扶養の可否 | 健康保険や年金に加入が必要になる |
| 106万円 | 一定条件の会社で勤務 | パートでも社会保険加入が義務になることがある |
| 150万円 | 配偶者特別控除の満額ライン | 控除額が減り始める |
※壁を超えても「損をしない働き方」もあるため、総合的な判断が大切です。
◆ まとめ:配偶者の収入と控除は“連動”している
- 配偶者の年収が103万円以下なら「配偶者控除」
- 103万円を超えても、201.6万円までは「配偶者特別控除」が使える
- 控除額は、配偶者本人の収入だけでなく、納税者本人の所得金額でも変わる
- 所得税だけでなく、住民税や社会保険の仕組みもセットで考えよう
第4章:扶養控除 - 子どもや親を支える人の税金を軽くするしくみ
◆ 扶養控除とは?
扶養控除とは、家族を養っている人の税金を軽くする制度です。
配偶者控除とは違い、「配偶者以外の親族(子ども・親など)」が対象になります。
具体的には、次のような人が対象になり得ます:
- 子ども(16歳以上)
- 大学生や予備校生など(収入がない場合)
- 親・祖父母(同居・別居問わず)
- 兄弟姉妹(障害などで扶養している場合 など)
◆ 扶養控除の対象となる条件
控除を受けるには、以下すべての条件を満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 対象者の合計所得が48万円以下 | 給与収入だけなら103万円以下が目安 |
| ② 納税者と生計を一にしている | 同居・仕送りなど「生活を共にしている状態」 |
| ③ 配偶者でないこと | 配偶者は別途「配偶者控除・配偶者特別控除」へ |
※「生計を一にする」とは、「お金の出どころが同じ(生活費や学費などを仕送りしている)」という意味です。別居でも可能です。
◆ 控除額は年齢で変わる!扶養親族の種類とは?
扶養される人の年齢や状況によって、控除額が異なります。
| 種類 | 対象者の条件 | 所得税 控除額 |
|---|---|---|
| 年少扶養控除 | 0~15歳 | 0万円 |
| 一般の扶養親族 | 16歳以上~18歳未満、または23歳以上 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満(※大学進学等が多い世代) | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上かつ納税者と同居 | 58万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上かつ別居(仕送り等) | 48万円 |
| 16歳未満 | 対象外(※児童手当など別の支援あり) | 控除なし |
◆ 「特定扶養親族」とは?
特定扶養親族とは、19歳以上23歳未満の扶養されている子どものことを指します。
- 高校卒業~大学卒業までのいわゆる“浪人・大学生”が該当することが多い
- 通常の扶養控除(38万円)よりも手厚い 63万円の控除
進学や予備校などで出費がかさむ時期だからこそ、税金面でも負担が軽くなる制度です。
◆ 特定親族特別控除の仕組み
対象:
- 年齢:19~22歳の扶養親族
- 所得範囲:合計所得58万円超~123万円以下(給与収入で123万~188万円程度)
控除額(所得税):
| 親族の所得 | 控除額 |
|---|---|
| ≤58万円 | 63万円(旧制度) |
| 58〜85万円 | 63万円 |
| 85〜90万円 | 61万円 |
| 90〜95万円 | 51万円 |
| 95〜100万円 | 41万円 |
| 100〜105万円 | 31万円 |
| 105〜110万円 | 21万円 |
| 110〜115万円 | 11万円 |
| 115〜120万円 | 6万円 |
| 120〜123万円 | 3万円 |
| >123万円 | 0円(扶養対象外) |
住民税でも類似の段階控除が適用されますが、控除額は所得税より少し低めに設定されています
◆ なぜ16歳未満の子どもは扶養控除の対象外なの?
「うちの子どもはまだ小学生だけど、扶養してるのに控除がないの?」と思われるかもしれません。
これは平成23年の税制改正(民主党政権下)で、16歳未満の子どもに対する扶養控除が廃止されたためです。
背景には、
- 児童手当(子ども手当)を拡充した代わりに、税の控除はやめた
ただし、扶養控除と引き換え条件の子ども手当は26,000円だったが、1度もその額を払われることもなく現在は1万円のみ。 - 所得控除より、手当による直接的な支援の方が公平でわかりやすいという方針
…という政策判断がありました。

26,000円の約束が一度も守られてないし、当時、下野してた自民党は子どもの扶養控除を無くすなんてけしからん!と声を大にして反対。そして公約に特定扶養控除復活を入れていたのに、政権取った後も復活しなかったんですよね。
民間だったら詐欺で訴えられてますよね。
と、言う意見もあり、2025年夏の参議院選挙において、年少扶養控除の復活を公約に掲げる野党も複数あります。しかし、この話をすると必ず
「扶養控除と児童手当の二重取りなんてありえない!」みたいなことを言う人がいるのですが、民主党が政権取るまでは両方ありました。そして現在も高齢者は年金を受給しながら公的年金控除を受けています。高齢者も子どもも働けない人ですからね。詳しくは「年少扶養控除は今はない!もしも復活するなら【N分N乗?扶養控除増額?】」を御覧ください。
◆ 住民税の扶養控除は違うの?
はい、住民税でも扶養控除はありますが、控除額が少し異なります。
| 種類 | 所得税 控除額 | 住民税 控除額 |
|---|---|---|
| 年少扶養控除(0~15歳) | 0円 | 0円 |
| 一般の扶養親族 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 58万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 48万円 | 38万円 |
※16歳未満はどちらも対象外です。
◆ よくある勘違いと注意点
- 「児童手当もらってるから控除もある」と思っている→×
- 「年末調整で勝手にやってくれるから大丈夫」→△
→子どもが大学に進学したときなどは、自分で変更届を出さないと反映されないことも。 - 別居でも扶養控除できる?→〇(仕送りの事実があればOK)
- 控除対象の子どもがアルバイトしてる→〇か×
→年収103万円超えていたら控除対象外になる可能性あり。
◆ まとめ:家族のライフステージに応じて見直そう
- 扶養控除は「子どもや親など、配偶者以外の家族」を支える人への税優遇制度
- 子どもの年齢、進学、親の高齢化などで控除額が変わる
- 16歳未満は対象外
- 扶養する家族に収入があるかどうかも重要
- 年末調整や確定申告で、正しく申告しないと“控除されない”ので注意!
第5章:障害者控除 - ハンディキャップを持つ人への税の配慮
◆ 障害者控除とは?
障害者控除は、納税者本人やその家族に障害がある場合に、所得税や住民税を軽減するための控除です。
生活に配慮が必要な人に対して、「税金を少しでも軽くして支援しましょう」という考えから設けられている制度です。
◆ 控除対象になる人は?
障害者控除の対象になるのは、次のいずれかに該当する人です。
【対象となる人】
- 納税者本人が障害者である場合
- 納税者の扶養親族や配偶者が障害者である場合(=扶養控除や配偶者控除と重複して適用可)
◆ 障害の程度によって控除額が変わる
| 区分 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) | 条件の一例 |
|---|---|---|---|
| 一般の障害者 | 27万円 | 26万円 | 身体障害者手帳3~6級、知的障害B程度など |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 身体障害者手帳1~2級、知的障害A程度など |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 特別障害者で、納税者と同居している扶養親族または配偶者の場合 |
◆ 障害の認定はどう判断するの?
障害者控除の対象かどうかは、次のような公的証明が判断材料になります。
| 種類 | 該当する証明書 |
|---|---|
| 身体障害者 | 身体障害者手帳(等級1~6) |
| 知的障害者 | 療育手帳(AまたはB)や医師の診断書 |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳(等級1~3) |
| 寝たきり高齢者等 | 要介護認定+市町村長の認定など |
※該当しそうな方がいる場合は、事前にお住まいの自治体や税務署に確認することをおすすめします。
◆ 控除額のイメージ
例えば、納税者本人に特別障害がある場合:
- 所得税:40万円の所得控除
- 税率10%の場合 → 実質税額が4万円軽減
さらに、同居している親が特別障害者であれば、75万円の控除が受けられるため、影響は大きいです。
◆ よくある質問と注意点
Q:控除は年末調整で自動で反映される?
→ A:申告が必要です!
勤務先に「障害者控除対象者」であることを申告しないと、年末調整では適用されません。
Q:どこに記載すればよい?
→ A:「扶養控除等申告書」などで該当欄に記載。確定申告する場合は該当項目に記入。
Q:親が特別障害者で施設に入っているけど、同居特別障害者になる?
→ A:ならない可能性が高いです。施設入所中で同居していないと「同居」とみなされません。
Q:介護保険の「要介護認定」だけではダメ?
→ A:原則不可。市区町村長の認定(「障害者控除対象者認定書」など)が別途必要です。
配慮を税で支える制度!手続きは忘れずに!
- 障害者控除は、本人または扶養親族・配偶者に障害があると受けられる
- 程度によって、控除額は27万円・40万円・75万円(所得税ベース)
- 年末調整や確定申告での申告が必要
- 手帳や診断書などの証明書類が判断基準になる
- 「同居特別障害者」は控除額が大きくなるため、条件の確認を!
第6章:ひとり親控除・寡婦控除 - 家族構成に配慮した税制の“変化と現在”
◆ そもそも「寡婦控除」ってなに?
「寡婦(かふ)控除」とは、夫と死別・離婚した女性や、子どもを養っている未婚の母などに対して、所得税・住民税を軽減する制度として設けられていたものです。
しかし、長年「女性限定」の制度だったことから、
「男女平等の観点で不公平では?」という批判が多くありました。
◆ 令和2年の改正:ひとり親控除が創設され、制度が大きく変わった!
令和2年(2020年)から、次のような改正がありました:
「ひとり親控除」の新設(男女問わず対象)
シングルマザーも、シングルファーザーも、同じ条件で適用!
「寡夫控除(男性限定)」は廃止
寡婦控除に一本化されたが、要件は引き続き「女性限定」
◆ 現在の控除制度は2本立て
| 名称 | 対象者 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
|---|---|---|---|
| ひとり親控除 | 男女問わず、未婚や離婚・死別で子どもを扶養している人 | 35万円 | 30万円 |
| 寡婦控除(女性のみ) | 配偶者と離別・死別した女性で、一定条件を満たす人 | 27万円 | 26万円 |
◆ 「ひとり親控除」の要件
以下のすべてに当てはまると、「ひとり親控除」が適用されます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 婚姻歴がない or 離婚・死別している | 法律上の配偶者がいないこと |
| ② 扶養親族に子ども(合計所得48万円以下)がいる | 所得税法上の「子」として判断 |
| ③ 本人の合計所得金額が500万円以下 | 住民税では所得制限が異なる場合あり |
※所得500万円超の人は「ひとり親控除」は受けられません。
◆ 「寡婦控除」の要件(女性限定)
扶養する「子ども」がいない場合でも、次の条件で「寡婦控除」が受けられます(ただし女性に限る)。
| 対象者 | 要件 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 死別・離別した女性 | 所得500万円以下+生計一の親族(子でなくてもOK)あり | 27万円 |
| 夫と死別し、子どもあり | 所得制限なし | 27万円 |
◆ 寡婦控除とひとり親控除、併用はできる?
いいえ、どちらか一方しか使えません。
そして、子どもを扶養していればより控除額の大きい「ひとり親控除」が優先適用されます。
◆ 住民税にも控除はある?
はい、住民税にも「ひとり親控除」「寡婦控除」が存在し、控除額は少し低めです。
- ひとり親控除:30万円
- 寡婦控除:26万円
※市区町村によって取り扱いが微妙に異なる場合があるので、気になる方はお住まいの自治体にも確認しましょう。
ひとり親控除・寡婦控除のよくある質問
Q:未婚のまま出産した場合も控除対象になる?
→ なります! 条件を満たせば「ひとり親控除」が受けられます。
Q:子どもがパート収入あるけど大丈夫?
→ 合計所得が48万円以下(年収103万円以下)なら扶養親族としてカウント可能です。
Q:シングルマザーとシングルファーザーで差はない?
→ ありません!「ひとり親控除」導入により、男女平等に適用されるようになりました。
制度改正で男女平等に。今は“誰でも使える”ひとり親控除へ
- 「寡婦控除」は女性限定で27万円
- 「ひとり親控除」は男女問わず、子どもを扶養していれば35万円
- 所得制限(500万円以下)に注意
- 年末調整や確定申告で申告しないと、控除は自動では適用されません!
第7章:勤労学生控除 - 働く学生への税制のやさしさ
◆ 勤労学生控除とは?
アルバイトをしている学生さんが、「自分で稼いだ分に税金がかかるのでは?」と不安に思うことは多いと思います。
そんな学生のために設けられているのが、この「勤労学生控除」です。
これは、勉強しながら働いている学生には、税金を少し軽くしてあげようという制度です。
◆ どんな人が対象になるの?
次の3つすべてに当てはまる人が「勤労学生」として控除の対象になります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 所得が給与所得など「勤労によるもの」 | アルバイト・パートなど |
| ② 合計所得が75万円以下(給与収入なら130万円以下) | 給与所得控除65万円+10万円(控除額) |
| ③ 学校に通っていること | 大学・短大・専門学校・高校・予備校など |
ポイント
- 「学校」は国公私立問わずOK
- 通信制・夜間制でも対象(教育機関であれば)
◆ 控除額はいくら?
| 種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
|---|---|---|
| 勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
※これは基礎控除とは別に受けられます。
◆ 親の扶養と両立できるの?
いいえ!できません!!
勤労学生控除を使うと、親の扶養から外れることになります。
なので、親の所得と比較して、どちらのほうが得かを計算して決めましょう。
◆ よく出てくる数字:「103万円」「130万円」「150万円」ってなに?
| 壁の名前 | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 所得税がかかり始めるライン | 給与収入103万円までは課税されない(基礎控除+給与所得控除) |
| 130万円の壁 | 社会保険の扶養から外れる可能性 | 親の扶養から外れて自分で保険料を払う必要あり |
| 150万円の壁 | 配偶者特別控除の満額がもらえる上限 | 親や配偶者の控除に影響する |
勤労学生控除が効いてくるのは「103万円超えても130万円以下」の間
たとえば、年収120万円の学生の場合:
- 所得税は本来かかるはずですが…
- 勤労学生控除(27万円)を受ければ非課税!
という形になります。
◆ 勤労学生控除の申請方法
- 会社員アルバイトの場合:年末調整時に「扶養控除等申告書」にチェック
- 確定申告をする場合:所定の欄に「勤労学生控除」を記入
- 申告しないと適用されないので、バイト先にきちんと伝えることが大切です!
◆ よくある勘違いと注意点
- Q:高校生でも使える? → はい、学校に在学中なら使えます
- Q:収入がバイト以外でも対象? → 雑所得・不労所得(配当や不動産収入など)は×。労働収入であることが必要
- Q:複数バイトでもOK? → 合算した年収で判定されます。バイト掛け持ちでも可
第8章:人的控除が適用される順番と注意点 - 組み合わせと落とし穴に注意!
◆ 控除が重なるってどういうこと?
人的控除にはいろいろな種類があります。
たとえば…
- 子どもを扶養している ⇒ 扶養控除
- しかも大学生 ⇒ 特定扶養親族控除
- 子どもに障害がある ⇒ 障害者控除
- 自分が未婚の親 ⇒ ひとり親控除
…このように、複数の控除が“重なる”ケースはよくあります。
ただし、なんでもかんでもダブル・トリプル適用できるわけではなく、控除ごとに「併用できるかどうか」が決まっています。
◆ 基本の考え方:「併用できる or できない」のルール
| パターン | 併用可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 扶養控除 + 障害者控除 | 〇 | 扶養している親族が障害者なら両方OK |
| 配偶者控除 + 障害者控除 | 〇 | 配偶者が障害者であればOK |
| 配偶者控除 + 配偶者特別控除 | × | どちらか一方のみ(所得次第で変わる) |
| ひとり親控除 + 寡婦控除 | × | どちらか一方(子どもがいればひとり親が優先) |
| 扶養控除 + 勤労学生控除 | × | 控除を受ける本人は、他人の扶養親族になれない |
| 配偶者控除 + ひとり親控除 | △ | 本人と配偶者が別、かつ要件満たすなら可能だが現実的には稀 |
◆ 所得控除の適用“順序”はある?
実際には、年末調整や確定申告のとき、所得控除は次のような順で適用されます:
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除(子どもや親など)
- 障害者控除
- 寡婦控除・ひとり親控除
- 勤労学生控除
これは「優先順位」というより、処理の流れと理解してOKです。
実務上は、税額計算に影響が出ないように整理されて処理されます。
◆ 控除を受けるための“手続き”を忘れずに!
どんなに条件を満たしていても、申告をしないと控除は適用されません。
| 控除名 | 必要な手続き(会社員の場合) |
|---|---|
| 扶養控除 | 扶養控除等申告書の提出 |
| 配偶者控除 | 同上(配偶者欄への記入) |
| 障害者控除 | 障害者手帳の写しなどが必要 |
| ひとり親控除 | 所得者本人の申告書チェック欄 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生であることの申告 |
確定申告をする人も、申告書の該当欄にきちんと記入しないと控除は反映されません。
◆ 控除の“対象になるかも”と思ったら…
自分や家族が控除の対象になるかもしれないと感じたら、以下のようなチェックポイントで判断しましょう:
- 扶養されてる人が年収103万円以下か?
- 障害者手帳を持っている家族がいるか?
- 自分がシングルで子どもを育てているか?
- 子どもが大学生・浪人生・19〜22歳であるか?
迷ったら、税務署や勤務先の人事・経理担当に確認するのが確実です。
人的控除は“申告しなければゼロ”になる!
- 重複OKな控除もあれば、併用できないものもある
- 所得や家族の状況によって適用の有無が変わる
- 年末調整や確定申告で、必ず手続きが必要!
- 条件に当てはまりそうなら、事前にチェックして備えておこう
第9章:人的控除を活かすために - 申告と手続きで差が出る!
◆ 控除は「自動で受けられるもの」ではない!
まず大前提として、どんなに条件を満たしていても――
自分で申告しない限り、控除は受けられません!
これは、会社勤めの方も、自営業の方も同じです。
◆ 会社員の方:年末調整で忘れずに!
提出すべき書類は?
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書 | 扶養親族や配偶者の情報を記載 |
| 基礎控除申告書 | 高所得者は別途必要(所得2,400万円超など) |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者特別控除を受ける場合に必要 |
| 所得金額調整控除申告書 | ひとり親・高額医療費などがある場合に使用 |
※勤務先から11月ごろに配布されることが多いです。
記入漏れや記載ミスがあると、控除が反映されず損をしてしまいます!
控除証明書の添付も忘れずに
- 障害者控除:障害者手帳の写しなど
- 老人扶養親族:住民票や年齢確認できる書類
- ひとり親控除:扶養している子の所得証明など(通常は申告書へのチェックで足りる)
◆ 自営業・フリーランスの方:確定申告でしっかり申告を!
確定申告書には、「人的控除」に関する記載欄があります。
主な記入ポイント:
- 所得控除の欄で、該当する控除額を記入
- 扶養親族の氏名・続柄・生年月日・所得の有無を正確に
- 添付資料が必要な場合(例:障害者手帳)は、控除の種類に応じて準備
e-Taxでも同様に申告できます。事前に必要な情報を整理しておきましょう。
◆ 控除対象者の「変化」に注意!
人的控除は、“今の家族構成”によって受けられるかが決まります。つまり、その年の途中で状況が変わったら、控除内容も見直しが必要です。
| こんなときは? | 見直すべき控除 |
|---|---|
| 子どもが16歳になった | 扶養控除の対象に追加できるかも |
| 子どもが大学に進学した | 特定扶養親族になり、控除額UPかも |
| 離婚した/配偶者が亡くなった | 配偶者控除から寡婦・ひとり親控除へ切り替え |
| 家族が障害者手帳を取得した | 障害者控除が適用できる可能性あり |
これらは、年末調整・確定申告時に自分で反映しなければ、反映されません!
◆ 控除の見逃しは“長期的な損失”に
たとえば、ひとり親控除(所得税で35万円)を5年間見逃すと、10万円以上の税負担差が生じることもあります。
また、障害者控除や特定扶養控除の見落としも、家計に大きく影響します。
◆ 控除の活用チェックリスト
- 扶養親族・配偶者の所得を確認したか?
- 年齢による控除の変化に気づいているか?
- 学生・障害者などの判定は最新か?
- 控除対象になりそうな人が増減していないか?
- 年末調整・確定申告できちんと申請しているか?
このチェックを毎年末に行うだけで、税負担を最小限に抑えることができます。
◆ まとめ:控除は「知っている」だけでは足りない!
- 控除の条件を満たしていても、申告しなければ1円も減らない
- 年末調整 or 確定申告の書類で正確に記入・申告することが重要
- 家族の状況が変わった年は、控除の見直しを忘れずに!
まとめ - 家族のカタチで変わる税金。正しく理解して節税しよう
◆ 人的控除は「あなたの家族構成に寄り添う制度」
税金というと、「収入が多い人ほどたくさん払う」そんなイメージがあるかもしれません。
でも実際には、扶養する家族がいる人や、生活に配慮が必要な人には、税金を軽くする制度がたくさん用意されています。
それが今回ご紹介してきた「人的控除」です。
人的控除は、単なる“お得な制度”ではありません。
その人の暮らしや家族の事情に、きちんと目を向けたしくみなのです。
◆ 控除を「使わない」ことは損をしているということ
- 「収入が少ないから税金も少ないだろう」と思っていても、本当はゼロになるはずの税金を払っていたということも…。
- 「年末調整を会社がやってくれるから大丈夫」と思っていても、申告漏れがあれば控除は受けられません。
つまり、知らないままでいると損をする可能性が高いのです。
◆ 今一度、チェックしてみましょう
- お子さんが16歳を迎えていませんか?
- 扶養しているご両親は高齢になっていませんか?
- お子さんが大学生になって、特定扶養親族の対象ではありませんか?
- ひとり親控除や障害者控除に該当する方はいませんか?
このように、人生のステージが変わるたびに、控除の適用範囲も変化します。
毎年見直すことで、払いすぎている税金を防ぐことができます。
◆ 正しく理解して、必要な人に届く制度に
税金の話は難しそうに感じるかもしれませんが、「人的控除」に関しては自分の生活に直接かかわる内容です。
家族を支える人、誰かに頼られる立場の人こそ、この制度を味方につけてください。
◆ 最後にひとこと
税金は「知らない人」から多く取るようには作られていません。
ただし、「知っている人」にだけ、ちゃんと優しくできる制度です。
人的控除は、あなたとあなたの家族のために用意された“やさしさの仕組み”。
しっかり理解して、きちんと申告して、賢く節税していきましょう!
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 暮らしと税2025年7月17日サラリーマンができる節税・社会保険対策 〜手取りを増やすための実践ガイド〜【初心者向け】
暮らしと税2025年7月17日サラリーマンができる節税・社会保険対策 〜手取りを増やすための実践ガイド〜【初心者向け】 副業と確定申告2025年7月15日ウッカリ2度税金を払ったらどうなる?返却は自己申告必要?
副業と確定申告2025年7月15日ウッカリ2度税金を払ったらどうなる?返却は自己申告必要? 雑談2025年7月15日わくわく広場 四谷三丁目店にお邪魔してみた!
雑談2025年7月15日わくわく広場 四谷三丁目店にお邪魔してみた!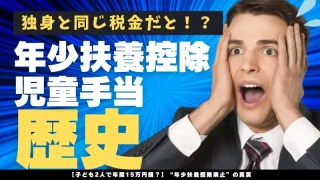 暮らしと税2025年7月14日【年少扶養控除の歴史】廃止と児童手当の関係!復活したらどうなる?
暮らしと税2025年7月14日【年少扶養控除の歴史】廃止と児童手当の関係!復活したらどうなる?

