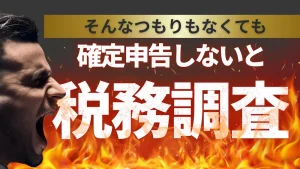先日、のんびりとニュースやSNSを見てたら、「基礎控除について、本当に知らない人が一定数いる」というポストが目に止まりました。
う~ん…確かに!!!
サラリーマンだったら、年末調整でサックリ終わった状態で源泉徴収票を渡されておしまい。
個人事業主でもe-taxなら自動で反映されますが、手書きでは基礎控除の欄が空欄になってる確定申告も見たことある。
本当はかなりありがたい制度なのですが、案外影は薄いのかも。
更に言うと、「節税節税!」という人が案外、基礎控除を含めた既存の制度を知らないことも多く、
事業と関係ない経費とか入れてきたりするんです。
と、なるともしかしたら「減税減税!」と言っている方でも、
ぶっちゃけ税制なんてしらねーよぉぉ!!!
という方がいてもおかしくない。
ここは一般人向け税の知識サイト「わかる税」の出番だと勝手に勘違いを発動して、基礎控除について、お伝えしたいと思います!
基礎控除とは?あなたの税金は、こうやって減税されてる
基礎控除とは?
基礎控除とは、誰もが生活に困らないように、生活にかかる最低限の費用は税金をかけないであげましょうね!というものです。
基礎控除の本質は「生存権」の保障
日本国憲法第25条には、こうあります。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
これはいわゆる「生存権」。
基礎控除は、この生存権を税制の中で具体的に反映した仕組みです。
つまり、「最低限の生活に必要な所得には、税金をかけませんよ」ということ。
国は「あなたが生きていくためのお金にまでは、さすがに課税しません」という立場を取っているのです。
ザックリ解説!所得税の決まり方!
基礎控除は、「所得控除」のひとつです。
控除とは、税金をかける前に「ここは差し引いて考えてね」という処理。
たとえば、あなたの年間の所得が300万円だったとしても、いきなりその全額に税率をかけるのではなく、様々な所得控除を引きます。
- 給与所得控除
- 基礎控除
- 社会保険料控除
などがサラリーマンなら引かれる最低限の所得控除です。
給与の総額から、これらを引いたもの(=課税所得)に税率をかけて、税金がかかります。
つまり、所得控除が多ければ多いほど、税金は減ることになります。
基礎控除とは?あなたの税金がこうやって減ってる
「基礎控除って、なんとなくありがたいらしい」
──そんな“ふんわり”した理解ではもったいない。
基礎控除は、実は憲法にもつながる“人としての当たり前”を守るための制度なんです。
基礎控除の本質は「生存権」の保障
日本国憲法第25条には、こうあります。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
これはいわゆる「生存権」。
基礎控除は、この生存権を税制の中で具体的に反映した仕組みです。
つまり、「最低限の生活に必要な所得には、税金をかけませんよ」ということ。
国は「あなたが生きていくためのお金にまでは、さすがに課税しません」という立場を取っているのです。
課税の前に“守るべき部分”を引く
基礎控除は、「所得控除」のひとつです。
控除とは、税金をかける前に「ここは差し引いて考えてね」という処理。
たとえば、あなたの年間の所得が300万円だったとしても、いきなりその全額に税率をかけるのではなく、様々な所得控除を引きます。
- 給与所得控除
- 基礎控除
- 社会保険料控除
などはサラリーマンなら引かれる所得控除です。
給与の総額から、これらを引いたもの(=課税所得)に税率をかけて、税金が来ます。
年収-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除=課税所得
課税所得×税率-税率にあった控除-税額控除=その年の所得税!!
という計算になります。
基礎控除を引き上げたらどう手取りは変わるのか!?
基礎控除がどういう根拠で出来たものなのかはご理解頂けたかと思います。
ですが、皆様の気になるのはやはり「自分たちの手取りにどれだけ影響あるの?」ということだと思いますので、解説していきます!
大前提
計算前提を以下の通りに置きます:
- 所得区分:給与所得者
- 所得控除は基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除の3つ
- 所得税率は累進課税に従って適用
- 住民税も10%で試算(ざっくり)
- 仮に、基礎控除は、所得税:123万円、住民税:113万円とする。
年収300万円の人
◆ 現行(基礎控除 所得税58万円 住民税43万円)
- 給与所得=年収300万円 - 給与所得控除 98万円
=202万円 - 課税所得=給与所得控除202万円-基礎控除58万-社会保険料45.8万
=98.2万円 - 所得税=課税所得98.2万円×税率5%
=4.9万円! - 住民税: 11.8万円
- 合計税額:16.7万円
◆ 引き上げ後(基礎控除 所得税123万円 住民税113万円)
- 給与所得=年収300万円 - 給与所得控除 98万円
=202万円 - 課税所得=給与所得控除202万円-基礎控除123万-社会保険料45.8万
=33.2万円 - 所得税=課税所得33.2万円×税率5%
=1.7万円! - 住民税: 4.8万円
- 合計税額:6.5万円
▶ 減税額:約10.2万円(=16.7万円 − 6.5万円)
▶ 減税率:61%
年収500万円の場合
◆ 現行(基礎控除 所得税58万円 住民税43万円)
- 給与所得=年収500万円 - 給与所得控除144万円
=356万円 - 課税所得=給与所得控除356万円-基礎控除58万-社会保険料72.4万
=225.6万 - 所得税=課税所得225.6万円×税率10%-税率に応じた控除額97,500
=12.8万円! - 住民税: 23.6万円
- 合計税額:36.4万円
◆ 引き上げ後(基礎控除 所得税123万円 住民税113万円)
- 給与所得=年収500万円 - 給与所得控除144万円
=356万円 - 課税所得=給与所得控除356万円-基礎控除123万-社会保険料72.4万
=160.6万 - 所得税=課税所得106.6万円×税率10%-税率に応じた控除額97,500
=6.3万円! - 住民税: 17.6万円
- 合計税額:23.9万円
▶ 減税額:約12.5万円
▶ 減税率:34%
年収300~500万のゾーンで年額10万円の手取りアップ!
基礎控除を123万円に仮に引き上げた場合、年間10万円以上、手取りが増えることになります。
しかも、年末調整で終わるので、経理担当は特に負担が増えることもなく、行政側も事務手数料をかけて給付金を払うわけでもなく、本人も確定申告をするわけでもない。みんなが最も手間かけずに出来るというのがメリットです。
誰かの手間になってしまうとそこにコストが発生してしまいますからね。
唯一あるとしたら、ソフト屋さんが「基礎控除の数値を…58から123に変更っと。テストして…ハイ終了!」とやってくれるだけです。そして、税理士事務所がこぞってソフト屋さんのソフトを使って業務効率化をして、皆様の年末調整を行う!!ソフト屋さんが大変かと思いますが、2024年の定額減税を乗り越えたソフト屋さんだったらきっと簡単なはず。
これまでに何度も変わってきた基礎控除
弊社(税理士事務所)に勤め始めたばかりの頃、
「基礎控除の38万円って、これじゃ絶対生活出来ないです。この数字はおかしいです。」
と、弊社の税務担当者に聞いたところ
「基礎控除なんてwww飾りみたいなもので、変わらないものだよwww」とバカにされたのを覚えています(根に持ってるわけではないですwでも、すごくおかしいと思ったのだけは覚えてます。)
先輩はそう言っていたのですが、歴史的に見ればかなり変化してきた控除です。
昔はもっと高かった?それとも低かった?
「物価も給料も昔より低いのに、税金だけ上がってる気がする…」
そう感じている方も多いかもしれませんが、まずは基礎控除の変遷をざっくり振り返ってみましょう。
基礎控除の歴史(抜粋)
| 年度 | 控除額 | 主な変更点 |
|---|---|---|
| 1947年 | 4,800円 | 日本国憲法施行のタイミングで |
| 1965~1990 | 9万→35万円前後 | 物価と共に漸増 |
| 2000年以降 | 一律38万円に固定 | 長らく据え置きが続く |
| 2020年 | 一律48万円に引き上げ | 同時に給与所得控除・公的年金控除を引き下げ(実質的な再編) |
| 2025年 | 一律58万円に引き上げ (2年間のみ段階的引き上げあり) | 所得再分配・実質減税として注目 |
このように、基礎控除は社会の変化や財政の状況に応じて何度も見直されてきた制度であり、「不変」だったわけではありません。
むしろ、歴史的に見直せば、1~5年程度のスパンで見直されてきた控除であり、昔はマスコミもこぞって「こんな金額で生活出来るか!」と批判の声を上げていたそう。中には、きちんと国民の生活のデータから、健康で文化的な最低限度の生活を出来る金額を算出した年もありました。
1987年、1997年消費税導入時・増税時には基礎控除の引上げがあった
消費税が上がるタイミング(3%、5%)では、消費税を支払うと国民の最低限の生活にかかる費用は増えてしまうので、それぞれ基礎控除額を上げていました。
ですが、8%の時は何もなし。10%に至っては、給与所得控除を10万下げ、基礎控除を10万アップで負担が増えただけ。事業者には基礎控除10万円アップしたものの、インボイスを導入するという始末です。(令和2年改正)
インボイスについては、弊社も多く対応をしておりますが、経理業務かかる作業量が増え、その結果、お客様には値上げのお願いをしております。本来でしたら、もっとお客様にプラスになることで値上げしたいのですけどね。
令和2年改正:48万円に上がったけど“トータルは変わらない”?
2020年(令和2年)には、それまでの38万円から48万円に引き上げられました。
ただしこのときは、給与所得控除や公的年金控除も引き下げられたため、「見かけの控除は増えても、実質的には変わらない人が多い」という調整型の改正でした。
これは「働き方の多様化」に合わせ、サラリーマンや年金生活者とフリーランス・自営業との控除の不公平をならす意図もありました。
令和7年改正:実質的な“増税調整”ではなく、明確な減税
今回の令和7年改正での引き上げは、背景が少し違います。
給与所得控除や年金控除の削減は伴っておらず、純粋に基礎控除額を増やす=実質的な減税となります。
このタイミングでの引き上げは、「物価高対応」や「低〜中所得層への支援」、「消費減税に代わる選択肢」としての性格が強いです。
高所得者は控除額が下がる?「所得制限」の存在
実は、令和2年改正から高所得者は基礎控除が減るという仕組みも導入されています。
- 合計所得2,400万円超:段階的に減額
- 合計所得2,500万円超:基礎控除ゼロ
つまり、基礎控除は「みんな一律」ではなく、所得の多い人ほど減らされる設計になっているのです。
令和7年(2025年)改正からは2,350万円から段階的に減額に変更になっていますのでご注意下さい!
基礎控除の減税効果は「年末調整!」12月の給与でドーン!
皆さん、12月のボーナスも終わった後、年内最後の給与がいつもより多くてびっくり!!という経験はありませんか?
アレこそが、基礎控除を初めてとする、所得控除の威力と言っても過言ではありません。
何かと出費がかさむ年末年始に、第2のボーナスのようで嬉しい人もいるはず!
年末調整の流れとしては…
- 日々の給与は基礎控除等を考慮せずに計算。
- 「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」などを提出→控除額が確定!
- 年末調整担当者がそれをもとに、年末調整ソフトに入力 →控除が反映
- 年末調整の結果を給与計算担当者に知らせる
- 給与計算担当者が給与で減税を反映!結果、給料の額面が増えてる!
という流れです。
つまり基礎控除などの控除が反映されるのは年末調整でガツンと調整をするので、そのタイミングで給料アップしているんです。でも、その増額分は控除で減税なんですよ。2025年12月は実に久しぶり(アラフォーの私が働き始めてから初めて)基礎控除が単独で上がるので、とっても楽しみにしております♪
だから、人によっては「減税された」ではなく「なんか給料がいつもより多いな」「先月残業したっけ?」と感じてる人もいるかもしれません。給料は会社が払うものだし、税金は取られる一方だと思ってたけど、その給料アップがまさかの減税だった!と気づくのにはある程度、税の知識が必要なんですよね。
給付とは違う!基礎控除による減税は手間がかからない
「年末調整は手間がかからないから良いよね~」と気安く言うと、弊社の鉄壁の年末調整チームの目からビームが出て丸焦げにされかねないのですが、給付と年末調整ならば…という比較をした場合、年末調整ならば、既に使っているソフトの数値変更をメーカー側(ソフト屋さん)がするだけで、年末調整担当者の負担は代わりません。一方で、給付の場合は、マイナポータルで給付用の金融機関の紐づけがされている場合はスムーズですが、そうでもない場合は、郵送手続きをして、記入された口座に振り込んで…と事務手数料が発生します。
参議院選挙のあとに配られる?と言われている給付金も2万円の給付金に対し、事務手数料9000円と言われています
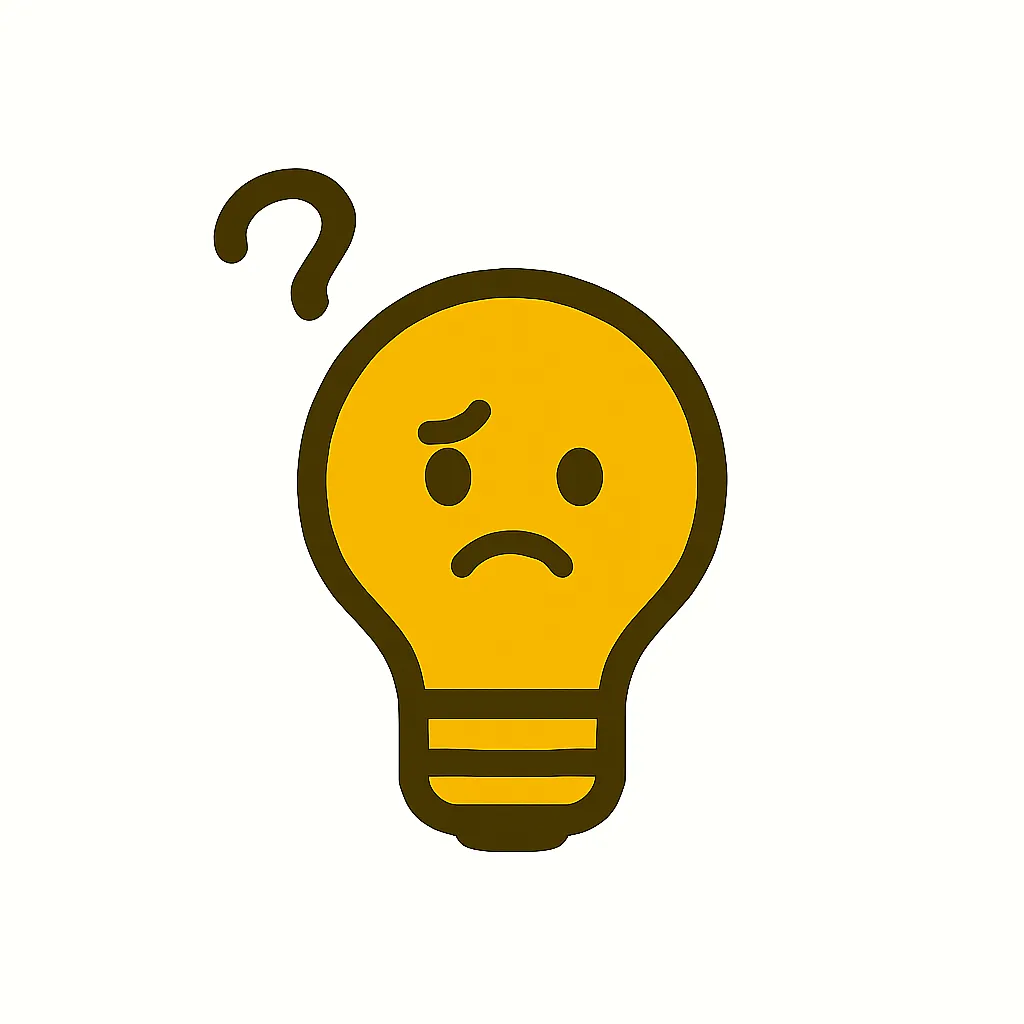
だったら、その事務手数料分も含めて30,000円、年末調整で返してほしい
という本音ダダ漏れで言わせて頂きます。
なんなら、児童手当も年間6回にワケなくて良い。年1回で14万円とかのほうが嬉しい。
というくらい、実際に手元に残るお金の方が気になるんです。
【まとめ】ようやく戻りつつある“当然の権利”
基礎控除の引き上げ──これは決して“優遇”や“支援”ではありません。
それは、国民の最低限度の生活を保障する“生存権”に基づく当然の制度が、ようやくまともな水準に戻された、ということに他なりません。
今までは“30年間削られたまま”だった、あなたの権利
私たちが働いて得たお金には税金がかかります。
でもその前に、憲法25条はこう定めています。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
この「最低限の生活」に必要なお金にまで課税することは、憲法の理念と矛盾します。
だからこそ、生活に必要な部分(=基礎控除額)は非課税にするのが原則です。
ところが、これまでの基礎控除は長年38万円に据え置かれ、ようやく2020年に48万円、そして今回2025年に58万円へと引き上げられます。
実態に比して、国が“あなたの生存権のライン”を過小に見積もってきたとも言えるのです。
でも、年間58万円で「最低限の衣食住」を出来る人ってどのくらいいますか?
私がひとり暮らしをしていた時の家賃の最低額は42,000円/月。年間50.4万円が家賃で6畳のワンルーム、壁うすすぎて隣の部屋のTVの音丸聞こえの部屋に消えてました。お米の値段も上がっている。夏は暑すぎてエアコン無しでつらすぎるし、猛暑で野菜が育たない。そんな中で年間58万円で生活って、ローンなしの持ち家で田んぼや畑を所有している人くらい???しか思いつかないんですが、彼らは彼らで最低限の生活には車が必須なので…うーん58万円で生活出来る人ってそんなにいる??ってリアルに考えるんですよ。
この58万円という数字が、リアルに近づくといいなぁと感じていますが、これには国民の声が必要であり、その前に国民の理解が必要ともいえます。
「支援される人」だけが得をする社会でよかったのか?
ここ数年、物価高騰を受けた政府の対策は、主に住民税非課税世帯への給付金に集中していました。
もちろん、それは必要な人への公助として一定の意味があります。
しかし、そうした制度の陰で、日々働き、税を納めながらもギリギリの生活をしている人たちが何の支援も減税も受けられずに取り残されていた
──という事実があったことは、見過ごせません。
頑張って這い上がろうとしている低所得者、子どもがいる中間層、何かと所得制限されてばかりの高所得者…
高所得者以外にはなったことあるけど、どの層だって、めっちゃ頑張ってるんですよ!!
超頑張ってるんですよ!!!
高所得者はおそらく、中学か高校ぐらいからめっちゃ頑張って、頑張り続けてる人なんですよ!
超頑張ってるんですよ!!!
氷河期だって、Z世代だって、それぞれの持ち場でそれぞれの仕事を頑張って、納税もしてる。
それなのに、「働いていない人はお金もらえて、働いてる人はなし!」という不公平なことしたらダメですよね?
今回の基礎控除引き上げは、「公助」ではなく「自助への尊重」
基礎控除が引き上げられたことによって、ようやく、
- 働く人は、自分で守る「自助」の力が少し補強
- 働けない人には、公助を用意
という公平な構図が成り立ちます。
これは、「支援」ではなく、憲法の理念に基づいた正当な“是正”であり、
あなたの権利が、少しだけ元に戻ったということなのです。
基礎控除が上がったら減税です!
さぁ!復習の時間ですよ!!
控除とは、「引き算しますよ!」の意味でした
基礎控除アップ=減税です!
そう考えると、今回の改正は小さなようで、実はとても大きな一歩だったのではないでしょうか。
なんせ30年近く動いていなかったものを動かすのって、大変ですよね。
皆様も、ものを動かす時、自分を動かす時、最初の1歩が一番重い…という経験はあるのではないでしょうか?
最後にもう一度、はっきり言います。
基礎控除は優遇ではない。
本来あるべき「税の公平」が、ほんの少しだけ戻ってきただけです。
その意味を、知っている人が増えていくことこそが、超重要だと感じております。
なんなら、基礎控除は毎年あげて行くくらいでちょうどいいかもしれません。
だって、毎年、物価上がっていますよね。
油も、米も上がった!牛乳も上がった!毎朝食べてるシリアルも上がった!
野菜の値段もこれ以上下がらないでしょうね。
だから、毎年基礎控除は見直したって良いんですよ。
その場合、一番泣くのは・・・我々税のコラムニストかもしれませんね…
すべてのページの基礎控除額を毎年変更して計算式の答えを変更…
消費税額を変えるより時間かかるかもしれません(笑)
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説
雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説 税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説
税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説 税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル
税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
免責事項
本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。
税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
本コラムの情報を用いて行う一切の行為およびその結果について、当サイトは責任を負いかねます。
実際の申告や手続き、具体的な判断が必要な場合は、国税庁・自治体等の公的情報をご確認のうえ、税理士などの専門家へご相談ください。