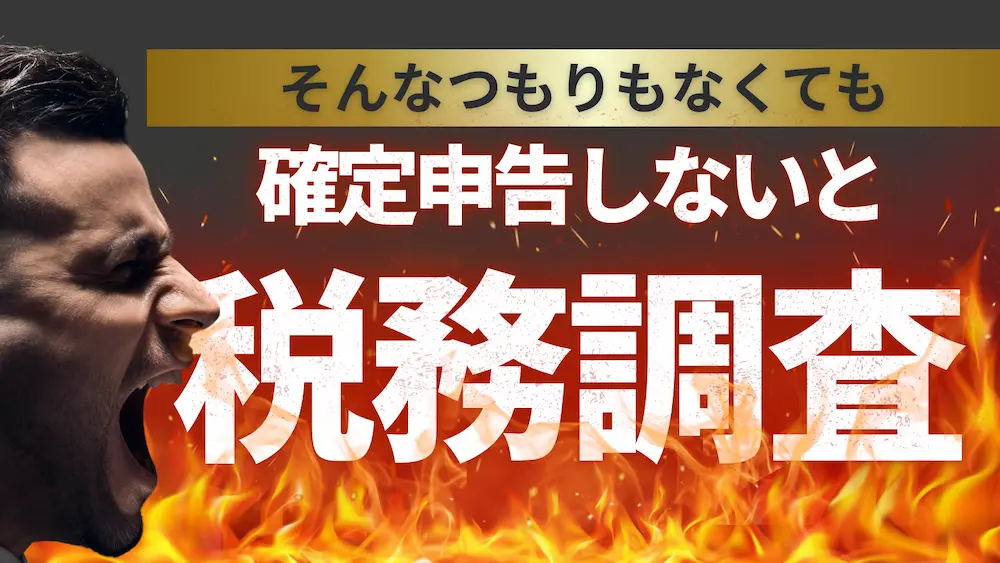
ここ数年で、インスタグラムやX(旧Twitter)、YouTube、ブログといったネット発の副業が一気に広がりました。中には、趣味で始めたSNS投稿がいつの間にか広告収入につながり、「あれ?ちょっとしたお小遣い稼ぎになってきたな」なんて人も多いはずです。
でも、その「ちょっとしたお小遣い」――。
実は立派な“所得”であり、税金の対象になること、ご存じでしょうか?
「月に数万円だし、わざわざ税金なんて…」
「会社にバレたくないから、申告しないで黙っておこう」
「副業の収入って確定申告しなくても大丈夫なんでしょ?」
――こんな声をよく耳にします。
たしかに、少額なら税務署にバレないんじゃ?と思いたくもなります。ところが、いまの時代は昔と違って、SNSやネット収入はデータとして“丸見え”になっているのが現実。
税務署も「ネット系副業は泳がせておいて、数年後に一気に税務調査で刈り取る」なんて、ちょっと怖い戦略をとっていることもあるのです。
このコラムでは、そんなネット系副業にまつわる「確定申告しないとどうなるか」を、税理士の視点から、わかりやすく&リアルに解説していきます。
5年間泳がされたあとに、ある日突然届く税務署からの封筒――
「しまった、やっておけばよかった…」と後悔しないためにも、今のうちに知っておきましょう。
副業収入はどこまでが申告必要?基準をおさらい
「副業の収入って、いくらまでなら申告しなくていいの?」
この質問、めちゃくちゃ多いです。SNSで副業を始めた人ほど「グレーゾーン」だと感じているはず。
しかし、はっきりとボーダーがあります!
そして、ルールもあります。
かつ、税務署にはマイルールは通用しません!
まず大前提として、副業で得た収入には原則として所得税がかかります。
ただし、状況によって申告義務がないケースもあるので、ポイントを整理しましょう。
「20万円ルール」の正体
よく聞く「20万円までは申告しなくていい」という話。
これは“給与所得がある人”だけに適用される特例です。
具体的には、
本業で年末調整を受けている人が、雑所得や事業所得などの合計が年間20万円以下なら、確定申告をしなくてよい(ただし、住民税の申告は必要)
という内容。
つまり、
- 給与以外の所得(ネット副業の広告収入など)が年間20万円を超えるなら、確定申告が必要です。
- 一方、個人事業主や年金生活者などは対象外なので、1円でも利益が出ていれば基本的に申告が必要です。
こんな副業収入も「申告対象」になる
ネット系副業でありがちな収入には、すべて課税対象の可能性があります。
| 副業の例 | 所得区分 | 申告の対象? |
|---|---|---|
| YouTube広告収入(Google AdSense) | 事業所得または雑所得 | ✔ 申告必要 |
| ブログ収益(アフィリエイト) | 事業所得または雑所得 | ✔ 申告必要 |
| インスタPR案件の報酬 | 事業所得または雑所得 | ✔ 申告必要 |
| X(旧Twitter)投げ銭(収益化プログラム) | 事業所得または雑所得 | ✔ 申告必要 |
| noteやKindleでの売上 | 事業所得または雑所得 | ✔ 申告必要 |
金額がいくらであっても、継続的に収入を得ている=事業性があるとみなされれば、「事業所得」とされることもあり、青色申告も可能になります(後述)。
「経費を引いたあと」の金額で判断する
ここで勘違いしやすいのが、「収入」ではなく「所得」で判断するという点です。
たとえば、年間で40万円の副業収入があっても、必要経費として30万円かかっていれば、所得は10万円なので申告不要になる場合があります。
しかし、経費を証明できないと否認されるリスクもあるため、領収書や記録は必ず残しておきましょう。
なお、ネットビジネスは自宅でおこなているケースも多く、極端な経費を計上して、税金を減らそうとする方もいらっしゃると思います。
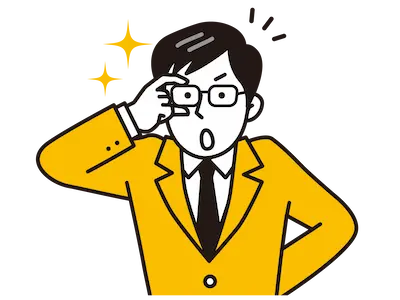
同業種で同じくらいの売上の場合で、異常な経費を上げている納税者はだ~れだ?
というようなAIも導入しているそうです。このシステム、あることは税理士も知っているのですが、税務調査官も「効率化していますよ~」とは教えてくれるけどどこまで分かるか・・・は秘密なようですが、税務調査官が言うのを妄想込みで書くと上の税務調査官のセリフになります。実際、近年は税務調査の質も上がって件数も追徴課税額もアップしています。
税務署は副業収入をどうやって把握しているのか?
「ネット副業なんてバレないでしょ?」「現金じゃないし、税務署も追えないでしょ?」
――そんな油断、今の時代には通用しません。
実は、税務署は“ネット副業の収入ルート”をかなり正確に把握できる仕組みを持っています。しかも、最近はAIも導入し、精度が高まっているんです。
ここでは、「どうやって税務署が副業収入を突き止めてくるのか」をリアルに解説します。
1. 銀行口座やクレジットカードは丸見え
税務署は、必要に応じて銀行口座の入出金情報やクレジットカード明細の開示を金融機関に請求することができます。これを「質問検査権」といいます。
たとえば、Googleから毎月数万円ずつ入金されていたり、「Amazon」「note」「ココナラ」などからの報酬が記録されていれば、それだけで副業の収入があることが分かってしまいます。
個人口座に振り込まれていても、隠し通せるものではありません。
私自身、複数のサイト運営をしており、それなりに副業収入がありますが、20万円以下であっても申告しています。
2. 海外のプラットフォームも情報提供している
昔は「Googleはアメリカの会社だから、日本の税務署にはバレないでしょ」と言う人もいました。たまに今でもそのようなことを仰るお客様もいらっしゃいます。でも、いまは海外の大手プラットフォームも、日本の税務当局と情報連携を進めています。
Google AdSenseやYouTube、Meta(Instagram)、Amazon、TikTok、noteなど、日本国内で収益を上げている人の情報は、日本の税務署に共有される可能性が高いです。またSNSは再生回数などを見れば、収益がどれほどかが計り知れますから、割と簡単にバレます。
とくに最近は「プラットフォーム報告制度(DAC7)」という国際ルールも進んでおり、“バレない副業”の時代は終わったと言ってよいでしょう。
実際、令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況では、主な取り組みの3番めに「インターネット取引を行っている個人に対する調査状況とあります。4番目が「無申告者似たする調査状況」と続きます。
弊社でもYouTuberのお客様のサポートをしておりますが、税務調査もまぁまぁ入っています。実際に税理士が申告してても入るし、他の業種よりプライベートとの線引が曖昧になりがちな分、税務調査が熾烈なことになっている印象があります。
3. SNSやブログからも足がつく
副業で人気が出れば、当然フォロワーも増えて拡散力も上がります。
ところが――それ、税務署の目にも留まりやすくなるんです。
実際、以下のようなケースでは税務署が動くこともあります。
- SNSで「月10万円の副収入!」などと自慢している
- noteで収益報告をしている
- YouTubeチャンネルの概要欄に「広告主募集中」などが書かれている
- ブログで収益化方法を解説している
税務署はネット上の情報をAIと人力の両方で監視しています。たとえば、インフルエンサーの名前でGoogle検索をかければ、収入のヒントがすぐに拾える時代です。
4. 税務署には「情報提供窓口」もある
こっそり副業していても、身近な人(元同僚、家族、取引先など)からの密告や通報で発覚するケースも意外と多いのが現実です。
国税庁のウェブサイトには「課税に関する情報の提供」という匿名通報フォームが用意されていて、「あの人、副業で収入得てるけど申告してないっぽい」といった通報が可能になっています。
嫉妬・トラブル・元恋人の逆恨み――
理由はともあれ、“人の目”から漏れるリスクも軽視できません。
「ネット副業=バレにくい」というのは、すでに過去の話。
いまはむしろ「情報の残りやすさ」「データの蓄積されやすさ」という意味で、ネット副業こそ“バレやすい副業”だという認識を持っておくべきです。
無申告で泳がされる5年間の恐怖
「副業収入なんてバレないでしょ」
「税務署が本気で動いたら、その時に考えればいい」
そんなふうに思っていませんか?
実は、税務署が“今すぐ”動かないのは、あなたを見逃しているからではなく、“泳がせている”からかもしれません。
ここでは、多くの人が知らない「5年泳がせ戦略」の実態と、その後に待ち受ける重たいペナルティについて解説します。
なぜ税務署はすぐに動かないのか?
税務署は、いきなり副業収入の調査に入るわけではありません。
なぜなら、「1年分だけ」では税額も小さく、効率が悪いからです。
そこで、税務署はこう考えます。
「この人、副業で申告してないな……。じゃあ5年分まとめて追徴しよう!」
そう、すぐには動かず、意図的に“泳がせておく”のです。
その間に、証拠(=入金履歴、SNSの活動履歴など)をじっくりと蓄積し、ある程度の額になったところで一気に調査に入る。これが税務署の“効率的な戦術”です。
税務調査官は、税の平等性を揺るがす不届き者にもきちんと税金を払わせる任務を請け負っている大事な存在です。そして、彼らのお給料も我々の血税から出ているので、彼らは誰よりもその重要性を理解しています。だからこそ、きちんと税金を納めていない人からはより効率的に、徴税出来るように彼らも工夫をしています。
無申告で待っている「5年分の追徴課税」
税務署が調査に入ると、過去最大5年間に遡って課税されます。
(悪質な場合は7年まで遡るケースもあります)
ここで発生するのが、本来の税金だけでは済まない、恐ろしい“加算”たちです。
実例:副業収入 年50万円(経費なし)のケース
- 本来の所得税・住民税:約10万円/年 × 5年 = 約50万円
- 延滞税(最大年14.6%) ≒ 数万円〜10万円超
- 無申告加算税(15〜20%) ≒ 7〜10万円
→ 合計:60万円以上の請求が一気に来る可能性も
これ、突然請求されたら、冷や汗どころじゃないですよね…。
「悪質」認定されるともっとヤバい
税務調査の中で「これは故意に隠してたな」と判断されると、重加算税(最大40%)が上乗せされることもあります。
さらに悪質と認定された場合には、
- 刑事告発 → 裁判 → 前科がつく
- 国税局査察部(いわゆる“マルサ”)が動く
- ネットや新聞に名前が出る
- 重加算税40%がかかる
なんて最悪のシナリオも…。
実際、YouTuberやインフルエンサーが「脱税容疑で逮捕」というニュースも増えており、ネット副業も“法の網の中”だと痛感させられます。
無申告だったYouTuberが「悪質」認定された事例
YouTuberの男性が報酬などとして約3600万円を得ていたにもかかわらず、確定申告をしていなかったとして、関東信越国税局の税務調査を受け、重加算税を含む約700万円を追徴課税された。
男性は当初「確定申告が必要と知らなかった」と言っていたが、パソコンの履歴から「税務調査を受けた場合どうするか」という内容の動画を見ていたことが判明。さらに、確定申告の必要性を伝えるメールも開封していたことから確定申告が必要だと知っていながら、無申告であったことを証明し、重加算税という重い罰を受けることとなった
引用元 フルクラウド税理士「知れば怖くない!税務調査の基礎知識」
この事例のポイントを整理します。
- 男性は、YouTubeの報酬があったが無申告だった
- 男性は、確定申告の必要性を認知していたが、税務調査がきたら「えー?申告必要だったの?知らんかったぁ~」としらばっくれたら無申告加算税だけで済むと思っていたと予想される(通常の税務調査なら、重加算税に至るまでの証拠を取ろうとはあまりしないから)
- 実際、税務調査は、パソコンを押収し、閲覧履歴から、申告の必要性を知っていた証拠を複数見つける
- 申告の必要性を認知しておきながら無申告だったよね!→はい、重加算税!!
ということです。
おそらく、この重加算税に一番驚いたのは、税務調査をいっぱい経験してきた税理士の方かもしれません。そのぐらい重加算税を課すためには、証拠が必要で時間を要するため通常の税務調査ではしないので、見せしめ的な意味もあったのではないかと思います。
国税庁、本気でネット系副業にもどんどんメスを入れるぞ!!と言ってるのではないかと思います。
しかも、このニュース3/11くらいに出てるんですよね。
確定申告期限内ギリギリのタイミングで出してくるあたり、税コラムニストとしては震撼と歓喜(?)が混じった声をあげました。
なので、税務調査に入っても無申告加算税程度だから大丈夫!とか思わないほうが良いですよ!
このコラムを読んだ貴方は既に、申告の必要性を知ってしまったのですから…
本当にごめんなさいね…でも、重加算税になって不幸を見るより、先に払うもの払ったほうがみんな幸せになれると思うんです…
家族や同僚を悲しませること、されないのをオススメします。一度失った信用は取り戻すのは大変ですから…
税務調査が来たらどうなる?リアルな流れ
「まさか本当に税務署が来るとは思わなかった」
これは、税務調査を受けた個人が口をそろえて言う言葉です。
ですが、最近は増えてますからね、個人への税務調査。副業がこれだけ多い上、納税意識がさほどないサラリーマンも多いのでより一層多くなるのかと思います。この機会に、ぜひ、税務調査のことも知っておきましょう♪
① 最初は事前通知から
税務調査の多くは「任意調査」と呼ばれ、事前に通知があります。
たとえばこんな封筒が届きます
「所得税に関する調査のお願い」
「○月○日に調査を行いますので、ご対応願います」
「必要書類(帳簿・領収書・通帳など)をご用意ください」

任意なら断ってもいいよね!?
と、思われるかもしれませんが、納税者には、実地調査に協力する義務があるため、拒否や辞退することは出来ません。
ただし、日程調整をすることは可能です。
さぁ、ここからが本番ですよ!!!
② 税務署員が自宅または税理士事務所にやってくる
通知された日時になると、税務署の調査官が2人1組で訪問してきます。
副業の場合、自宅を仕事場としていたり、そもそも税理士を付けていなかったりするため、自宅訪問されるケースも少なくありません。
税務調査官は先に貴方のことをよーく調べています。家族構成や家族の納税状況まで。
そうではないと出てこない質問というのも我々税理士事務所は経験済みでございます。
ぶっちゃけ、税務調査の7割は税務調査官が来た時点で済んでて、残り3割の証拠を抑えに来る…という程度の感じだと思っておいた方が良いです。
つまり、税務調査が来る…という時点でもうほぼ「何かしら」の疑惑を持たれているということです。
③ よくある“言い訳”は、通用しない
副業の無申告で税務署が来たとき、多くの人が口にするセリフがあります。
- 「知らなかったんです…」
- 「副業じゃなくて趣味なんです」
- 「友達からの謝礼で…」
- 「少額だし、そんなに重要じゃないと思って…」
でも、調査官は冷静に言います。
「では、なぜ通帳に毎月同じ名義で振り込みがありますか?」
「YouTubeで“月○万円稼いでます”と発信されていますよね?」
「それを使って生活費を払っていますよね?」
――通用しません。
言い訳よりも、素直に協力する方が減点は少なく済むこともあります。
④ その後に待っている“修正申告”と“追徴課税”
調査の結果、無申告が発覚した場合は、次のステップへ進みます。
- 修正申告:過去の収入を正しく計算し、申告をやり直す
- 追徴課税:延滞税・加算税を加えた金額を納付
額にもよりますが、数十万円~百万円単位の支払いになるケースも珍しくありません。
「もっと早く申告しておけばよかった…」
そう嘆いても、後の祭りです。
⑤ 悪質認定されれば、人生が変わることも
もしも、「意図的に隠していた」「何度も指摘を無視した」と判断されれば、
- 重加算税(最大40%)
- 刑事告発・略式起訴・罰金刑
などの処分が下る可能性もあります。
ネット副業は公開性が高いため、メディアに名前が出るリスクもあります。
つまり、副業どころか本業の信用・人生設計すら崩れる可能性もあるのです。
先ほども書いた通り、既にネット系副業(YouTube)でドカンと重加算税の例もありますからね!
まとめ!
ネット副業は「バレる前提」で備えよう
インスタ、X(旧Twitter)、YouTube、ブログ…
個人でも自由に収益を得られる時代。
楽しく稼げるネット副業ですが、「税金」という現実からは逃れられません。
むしろネット副業こそ、
- 収入の記録が明確に残る
- SNSやメディアで露出が増える
- プラットフォームから税務署への情報提供もされる
という点で、「バレやすい副業」だということを忘れてはいけません。
泳がされる5年間、そのツケは重い
税務署は、あえてすぐに動きません。
証拠を蓄積し、5年分まとめて一気に刈り取る。
その時には、所得税・住民税に加え、延滞税+加算税(最大40%)、最悪は刑事告発や前科…
という重たいペナルティが、一括でやってきます。
副業で得た“ちょっとしたお金”が、“人生最大の請求書”に化けるかもしれません。
今こそ、「申告と節税」の第一歩を
大事なのは、「バレないようにする」ではなく、「正しく申告して、節税も考える」というスタンスに切り替えることです。
- 青色申告で控除や経費をしっかり活用
- 副業が大きくなったら、税理士に相談
- 確定申告ソフトやアプリを使って手軽に申告
いまはスマホひとつで申告できる時代です。
「怖いから放置」ではなく、「わかる範囲でやってみる」で、税務署からの評価も全然違います。
もし、あなたが無申告なら…バレてから泣くより、今やったら大丈夫だから安心して!!
「えっ、自分も申告対象だったの?」
「もしかして、今、泳がされてる???」
そう気づいたあなたは、今が行動のタイミングです。
税務署は、知らなかったからといって容赦はしてくれません。
でも逆に言えば、今から、自ら期限後申告をすれば税務署がわざわざ税務調査をすることもなく、自ら延滞税をちょこっと払って終わります。
実は、税務調査が入る前に、自ら申告したほうが税金も安く済みます。税率が違う上、延滞期間も短くて済むので2重の意味で安くすみます。
税制は素直に申告し、ちゃんと納税する人には意外と優しく出来ています。
ネット副業が「人生を豊かにする手段」になるか、「税務リスクで壊される罠」になるか――
それは、あなたの選択次第・・・
人生にプラスになる選択をされることをオススメします。
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説
雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説 税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説
税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説 税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル
税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
免責事項
本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。
税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
本コラムの情報を用いて行う一切の行為およびその結果について、当サイトは責任を負いかねます。
実際の申告や手続き、具体的な判断が必要な場合は、国税庁・自治体等の公的情報をご確認のうえ、税理士などの専門家へご相談ください。


