こんにちは!そこそこツイ廃疑惑のわかる税編集部です!
今日も、SNS上で聞こえた一般人の税金のお悩みにお答えしたいと思います!
本日のお悩みはざっくりいうと
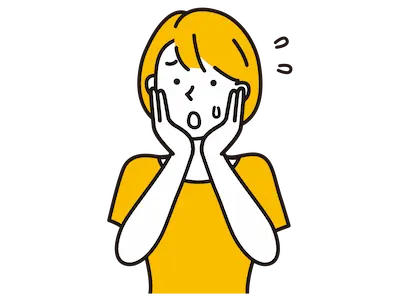
夫が相続対策のために、双子のどちらかを夫の両親の養子にしようとしている!お金のために子どもを売るようで絶対いや!!
という内容です。
う~ん・・・これは難しい問題!!ただ単に、相続税を下げれば良い・・・という問題でもないので、ちょっと冷静に考えたほうが良いかと思う課題でもあります。家族・・・そして、双子の意思も尊重する必要があると思いますね・・・
相続は「争族」というくらい、身内間で不仲になる原因にもなります。
ぶっちゃけ、争族を見すぎて、弊社の相続税担当者は「遺産はないほうが良い!」と言い出す始末。
お金も大事だけど、お金より大事なものを大事にしながら、お金も大事にしてほしいなぁと願いながら、執筆させて頂きます。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
まず「養子縁組」には大きく2種類あります。
- 普通養子縁組
→ 実の親との親子関係を残したまま、新たに養親との親子関係が加わります。
→ したがって、子どもには「実父母」と「養父母」の両方が親として存在することになります。 - 特別養子縁組
→ 家庭裁判所の審判が必要で、原則6歳未満の子どもが対象。
→ 実父母との親子関係は完全に切れ、養父母との関係のみが残ります。
→ 実の両親から見れば「完全に子どもではなくなる」という制度です。
SNSでのケースは、祖父母の相続税対策のためなので「普通養子縁組」にあたります。
なので、普通にご両親と生活をすることになります。
離婚時も、祖父母と養子の関係は続きます。
養子が相続税に与える影響は?
相続税の計算では「基礎控除額」が重要です。
基礎控除額は、
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
例えば、夫の両親の遺産が10億円あった場合を考えます。
相続人が「子ども2人」なら法定相続人は2人 → 基礎控除額は4,200万円。
もし孫の1人を養子にすれば、法定相続人が3人になり → 基礎控除額は4,800万円。
つまり相続税の負担が軽くなるというのが「養子縁組で節税できる」と言われる理由です。
ただし!「2割加算」の落とし穴
養子が孫である場合、相続税には「孫への相続税は原則2割加算」というルールがあります。
つまり、孫が養子になって遺産をもらうと、本来の税額に2割上乗せされてしまいます。
祖父母の財産が大きいケース(10億円級)では、この「2割加算」の影響が相当重いです。
単純に「基礎控除が増える=節税になる」とは言い切れません。むしろ逆効果になる場合もあります。
なので、このページでザックリと「そういうことなのねぇ」と理解したら、実際に遺産額と相続人でシミュレーションをするのがよろしいかと思います。
養子の人数には制限がある
国税庁は「養子縁組を乱用した節税」を防ぐため、相続税法上でカウントできる養子の数に制限を設けています。
- 実子がいる場合 → 養子は 1人まで
- 実子がいない場合 → 養子は 2人まで
SNSのケースでは実子(夫)がいるため、孫を養子にしても「基礎控除の計算に入れられるのは1人だけ」となります。
シミュレーション:10億円の遺産を相続した場合
養子がいる場合の節税効果は実は一次相続(祖父母が亡くなった時)よりも、二次相続(孫の親が亡くなった時)を合計したときに一番効果を感じられます。
なので、ココでは一次相続と二次相続で比較してみたいと思います。
前提条件
- 祖父の遺産総額:10億円(=100,000万円)
- 祖母はいない(配偶者控除なし)
- 双子(実子2人)。ケース②では双子のうち1人が祖父の普通養子(孫養子)
- 借金・葬式費用・小規模宅地等の各種特例は考慮なし
なお、相続税の計算は至ってシンプルです。
(特例などを活用して、税金を抑えようとするとめちゃくちゃ難しくなります)
- 相続税の基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(= 3,000 + 600×人数[万円])
- 各人の課税取得(按分額):(遺産総額 − 基礎控除) ÷ 法定相続人の数
- 相続税(各人):(各人の課税取得 × 税率) − 速算控除額
- ※ 孫が相続人の場合は上記税額×1.2(=2割加算)
一次相続:祖父 → 相続人
ケース① 養子なし(相続人=父のみ)
- 基礎控除
3,000 + 600×1 = 3,600万円 - 課税遺産総額
100,000 − 3,600 = 96,400万円 - 各人の課税取得(父のみ)
96,400 ÷ 1 = 96,400万円 - 税率適用(6億超 → 55% − 7,200万円)
相続税(父)= 96,400×0.55 − 7,200 = 45,820万円 - 父の手元に残る金額
96,400 − 45,820 = 50,580万円
ケース②(孫を養子に:相続人=父+孫の2人)
手取り
父:47,900 − 19,750 = 28,150万円
孫:47,900 − 23,700 = 24,200万円
(一次相続の手取り合計=52,350万円)0万円の差)
- 基礎控除
3,000 + 600×2 = 4,200万円 - 課税遺産総額
100,000 − 4,200 = 95,800万円 - 各人の課税取得(父・孫とも)
95,800 ÷ 2 = 47,900万円 - 税率適用と税額(3億超〜6億以下 → 50% − 4,200万円)
相続税(父)= 47,900×0.50 − 4,200 = 19,750万円
相続税(孫=2割加算)= {47,900×0.50 − 4,200}×1.2
= 19,750×1.2 = 23,700万円 - 手元に残る金額
父:47,900-19,750=28,150万円
孫:47,900-23,700=24,200万円
合計:52,350万円
二次相続:父の死亡 → 双子(実子2人)
ケース①(養子なしの続き:父の遺産=50,580万円)
- 基礎控除
3,000 + 600×2 = 4,200万円 - 課税遺産総額
50,580 − 4,200 = 46,380万円 - 各人の課税取得(双子2人)
46,380 ÷ 2 = 23,190万円 - 税率適用(2億超〜3億以下 → 45% − 2,700万円)
相続税(各子)= 23,190×0.45 − 2,700 = 7,735万円 - 子の手元に残る金額
各子:23,190 − 7,735 = 15,455万円
合計:30,910万円
ケース①のトータル
一次税:45,820万円
二次税:7,735×2=15,470万円
総税額=61,290万円(約6.13億円)
最終手取り(子2人合計)=30,910万円(約3.09億円)
10億円あった資産が祖父から孫になるときには3.09億円になってしまいました。
ケース②(孫を養子にした続き:父の遺産=28,150万円)
- 基礎控除
3,000 + 600×2 = 4,200万円 - 課税遺産総額
28,150 − 4,200 = 23,950万円 - 各人の課税取得(双子2人)
23,950 ÷ 2 = 11,975万円 - 税率適用(1億超〜2億以下 → 40% − 1,700万円)
相続税(各子)= 11,975×0.40 − 1,700 = 3,090万円 - 子の手取り
各子:11,975 − 3,090 = 8,885万円
合計:17,770万円
ケース②のトータル
一次税:19,750(父)+23,700(孫)=43,450万円
二次税:3,090×2=6,180万円
総税額=49,630万円(約4.96億円)
最終手取り=二次の子合計17,770万円+(一次で孫が得た)24,200万円
= 41,970万円(約4.20億円)
最終比較(数字で一目!!)
孫を養子に:総税額 4.96億円 / 最終手取り 4.20億円
→ 差:手取り+約1.11億円(孫養子の方が残る)
養子なし:総税額 6.13億円 / 最終手取り 3.09億円
一次相続だけでも2,000万円の差が生じます。
この差額だけでも、医学部いけちゃうくらいの差額ではあります。
では、養子にされた双子の一方だけがお金持ちになるのか?
① 相続する場面の違い
- 祖父母の相続
養子になった子は「祖父母の法定相続人」になります。
つまり祖父母が亡くなったとき、養子になった子だけが祖父母の財産を相続する権利を持ちます。
一方、養子にならなかった双子は、祖父母とは「ただの孫」であり、相続権はありません(遺言で指定されれば別です)。
➡ この段階では「養子になった子の方が有利」です。 - 父(夫)の相続
普通養子縁組の場合、実の親との親子関係は切れません。
したがって、養子になった子も、ならなかった子も、父が亡くなったときには「子ども」として平等に相続できます。
➡ ここでは双子に差はつきません。
② 財産の分配の実際
祖父母が10億円持っていて、その一部を養子になった子が直接相続すれば、
「養子になった子の名義で財産を得る」ことになります。
養子にならなかった子は祖父母からは1円ももらえません。
結果として、祖父母からの財産分配に差が生じるのです。
もちろんその後、親が「公平に分けてあげたい」と考えて遺言や生前贈与で調整することも可能ですが、それは親の意思次第。制度上は「片方だけが得をする」構造になります。
③ 家族トラブルの火種
実際の相続実務でも「兄弟姉妹のうち、養子になった子とそうでない子の間で不公平感が生まれた」というトラブルは珍しくありません。
法律上は整合性があっても、感情的には「なぜ自分だけもらえないのか」「兄弟で差をつけられた」と恨みを残すケースがあります。
相続を見てきて思うこと
大概の場合、祖父母、両親の順番で他界していきます。
残された双子がどのように暮らしてほしいか…
自分が亡きあと、何が子どもを支えてくれるのだろうか…そんな想いこそが「本当の遺産」だと思うんですよね。
お金はその形でしかないと感じております。
双子を平等に扱いたい場合は、法定相続人とか2割加算とか、お金のことばかりに気を取られることなく、相続を考えるのをおすすめします。
家族にとって何が一番大事か…はそれぞれの家庭によって異なるかと思います。
私の知人で、偶然、結婚する彼女の実家が超富裕層だった知人は義父に
「我が家の家訓は【兄妹仲良く】です。」
と言われたと聞きました。聞くところによると、義父の親の相続は兄弟で揉めてしまい大変だったとか…
お金によって、兄弟姉妹の関係が悪くならぬように配慮するのも、親の務めとのことです。
そんなわけで、ここで第三案を検討しましょう!!
シミュレーションケース③
父+養子孫+非養子孫の3人で分ける場合
ケース②では、養子の効果を感じられたかと思います。
ですが、これではお金持ちになる孫と、そうではない孫が生じてしまう…
これでは兄弟姉妹が仲良く過ごせなさそうですよね。
祖父母、両親が亡くなった後、兄弟姉妹は仲良く暮らしてほしい…
困ったときはお互い様の精神で助け合ってほしい…
なので、次は、【孫は一人養子にするけど、「もう一人の孫も平等に相続してね♪」という愛ある遺言書を残された場合】のシミュレーションをしてみましょう!!
一次相続(祖父 → 父+孫2人)
- 基礎控除:3,000 + 600×2 = 4,200万円
- 課税遺産総額:100,000 − 4,200 = 95,800万円
- 各人の課税価格(3等分した場合):95,800 ÷ 3 ≒ 31,933万円
相続税(速算表:3億〜6億 → 45% − 2,700万円)
- 父:31,933×0.45 − 2,700 = 11,766万円
- 養子孫(2割加算):(31,933×0.45 − 2,700)×1.2 = 14,119万円
- 非養子孫(遺贈なので2割加算):同じく 14,119万円
手元に残る金額
- 父:31,933 − 11,766 = 20,167万円
- 養子孫:31,933 − 14,119 = 17,814万円
- 非養子孫:31,933 − 14,119 = 17,814万円
👉 一次合計手元に残る金額=55,795万円
👉 一次相続の税額合計=40,004万円
二次相続(父の死後 → 孫2人)
- 父の財産:20,167万円
- 基礎控除:3,000 + 600×2 = 4,200万円
- 課税遺産総額:20,167 − 4,200 = 15,967万円
- 各人の課税価格:15,967 ÷ 2 ≒ 7,984万円
相続税(速算表:5,000万〜1億 → 30% − 700万円)
- 各子:7,984×0.30 − 700 = 1,695万円
手元に残る金額
- 各子:7,984 − 1,695 = 6,288万円
- 合計:12,576万円
👉 二次の税額合計=3,390万円
トータル(一次+二次)
- 総税額=40,004 + 3,390 = 43,394万円(約4.34億円)
- 最終手取り(養子孫+非養子孫+二次で受け取った双子)
= 17,814 + 17,814 + 6,288 + 6,288
= 48,204万円(約4.82億円)
3つのシミュレーションをまとめるとこうなりました!
| ケース | 相続パターン | 総税額 | 最終的な手取り(子や孫に残る合計) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ケース① | 養子なし(父のみ相続 → その後双子へ) | 約 6.13億円 | 約 3.09億円 | 最も税負担が重い。二次相続で多く税金がかかる。 |
| ケース② | 父+孫(養子)の2人で相続 → その後双子へ | 約 4.96億円 | 約 4.20億円 | 節税効果あり。ただし「養子になった孫」と「ならなかった孫」に不公平が残る。 |
| ケース③ | 父+孫2人(うち1人養子、もう1人は遺言で遺贈) → その後双子へ | 約 4.34億円 | 約 4.82億円 | 税負担が最も軽く、最も多く残る。双子も両方祖父から直接相続し、不公平感が少ない。 |
結果的に、「孫には平等に相続してね!」と遺言書を残された場合が一番相続税が安く済む結果になりました。
まとめ!!
養子も基礎控除額をあげられるので効果的ではあるのですが、それ以上に孫を平等に遺産を分配することで税金は抑えられる結果になりました。
それだけではなく、不平等感も解消出来ます。
しかし、これは全て平等に分配出来る現預金などだった場合のみ…
現実には土地だったりするので厳密に平等に分配というのは難しいものがあります。
それぞれの家族には、それぞれの形があるので、お互いに尊重しながら、元気なうちに相談をしておくのをオススメします。
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 副業と確定申告2026年1月15日令和9年から!青色申告75万円控除の内容とは!?
副業と確定申告2026年1月15日令和9年から!青色申告75万円控除の内容とは!? 雑談2026年1月14日電気自動車(EV)への課税はどう変わる?「公平な負担」を目指す新ルール【税制改正2026】
雑談2026年1月14日電気自動車(EV)への課税はどう変わる?「公平な負担」を目指す新ルール【税制改正2026】 税の仕組み2026年1月13日国民年金の第3号被保険者とは?制度ができた理由と歴史を年表でわかりやすく解説
税の仕組み2026年1月13日国民年金の第3号被保険者とは?制度ができた理由と歴史を年表でわかりやすく解説 雑談2026年1月9日当座預金って何?普通預金との違いと必要なケース、起業時の口座の分け方まで解説
雑談2026年1月9日当座預金って何?普通預金との違いと必要なケース、起業時の口座の分け方まで解説


