あの騒動から5年、「2,000万円」は過去の話?
2019年、「老後資金が2,000万円不足する」という金融庁の報告書が世間を大きく騒がせました。
当時は「年金がもらえないのか」「そんなに貯められない」と不安の声が噴出し、報告書は事実上の撤回に追い込まれたほどです。
しかし、5年が経過した今、あらためて当時の試算を見直すと、ある重要な前提が抜けていたことに気づきます。
それが「物価上昇(インフレ)」です。
「老後2,000万円問題」とは何だったのか?
まず2019年のことなので思い出してみましょう!
金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」が2019年に公表した報告書では、次のようなモデル世帯を例に挙げていました。
- 夫65歳、妻60歳の無職の夫婦
- 公的年金等の収入:約21万円/月
- 支出:約26万円/月
- 毎月の赤字:約5万円
- 老後30年間での不足額:5万円 × 12か月 × 30年 = 1,800万円(≒2,000万円)
これが「老後2,000万円問題」と呼ばれるようになった計算根拠です。
年金の負担に対してもらえない!!と不満が続出し、報告書は撤回となりましたが、2000万円問題が解決したか…といえばノー。
NISAやiDeCoや企業DCなどの制度によって老後資金を作っている人はまだまだ少ない状況です。
2,000万円で足りるという“前提”にご注意
実はこの報告書、物価の上昇を一切織り込んでいません。
つまり、「今と同じ生活費で30年間過ごせる」という、かなり楽観的な見通しに基づいています。
けれど、現実には物価は年々少しずつ上昇しています。
特に2022年以降は、エネルギー・食品・サービスを中心に、家計をじわじわ圧迫するインフレが続いています。
そもそもが、2012年末に安倍政権が始めた「アベノミクス」は緩やかなインフレ(2%)を目指していたのにもかかわらず、老後資産の計算にインフレ予測を入れてなかったのはお粗末としか言いようがないです。私個人の老後資産の計算エクセルは3%で計算しています。老後に「困った!」となってからでは遅いので厳しめに。ですが、リアルにどのくらいインフレしているのか、見てみましょう!
実際のインフレ率(消費者物価指数CPI)の推移
| 年度 | インフレ率(前年同月比) | 特徴 |
|---|---|---|
| 2019年 | +0.6% 前後 | 消費増税の影響も軽微 |
| 2020年 | ▲0.2%(デフレ) | コロナ禍で一時的に物価下落 |
| 2021年 | ±0% 前後 | 物価はほぼ横ばい |
| 2022年 | +3.0% 前後 | 電気・ガス・食品が高騰 |
| 2023年 | +3.1% 前後 | 外食・サービスも値上がり |
| 2024年 | +2.7% 前後 | 高止まり傾向 |
| 2025年 | +3.1%(現時点) | 米や加工品など生活必需品中心の上昇が継続中 |
この6年間の累積上昇率は、ざっくり計算すると毎年3%上昇。結果的に2021年と比較すると13%ほど上がっています。
つまり、「2019年時点で月25万円で暮らせていた人」が、2025年には月27〜28万円必要という現実。
「嗚呼、分かる…うちもそう…。」という方、多いのではないでしょうか?
我が家では、コロナ前は78円で買っていました。最安値は68円。鶏むね肉が38円でした。今では鶏もも肉99円が我が家の周りでは最安値。なのに給料は・・・上がっていません…。
米・食料品の値上がりは生活直撃
とくに家計に響くのが、「米」や「野菜」などの主食・日常食の上昇です。
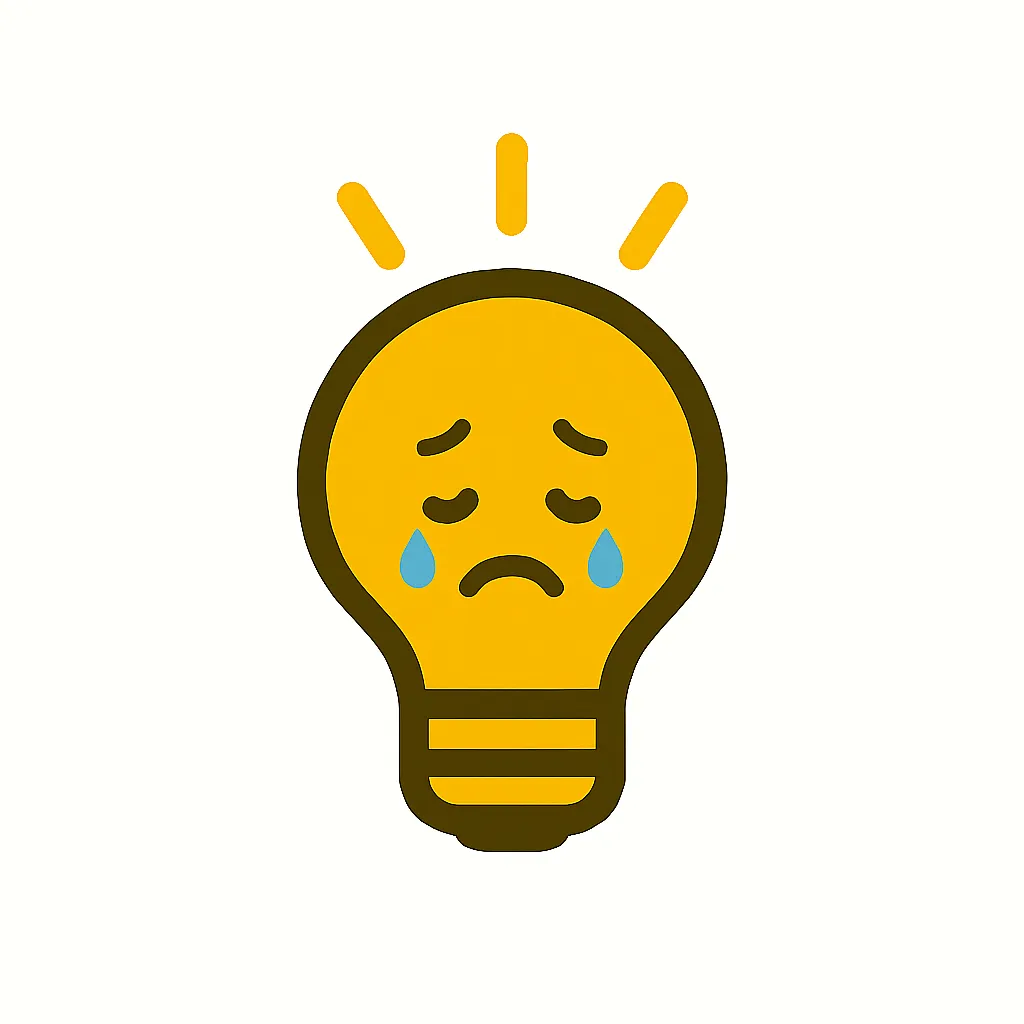
2019年には5kgで2,000円前後だったお米が、2025年現在では2,700〜3,000円という地域も珍しくありません。
つまり、「食費は毎月数千円〜1万円近くアップしている」という家庭もあるでしょう。
こうした“体感インフレ”は、統計よりも生活に直結するインパクトを持ちます。
インフレは“収まっても戻らない”
2025年現在、インフレ率は落ち着きつつありますが、「価格が元に戻る」わけではありません。
物価は“高くなったところで安定”するだけで、2022年以前の水準に戻ることは期待できないのが現実です。
物価はもとに戻ることはないのであれば、税金や社会保険料などが安くなるか、給料が上がるか…
のどちらかがなければ我々庶民の生活はラクになることはありません。
では、インフレを考慮したら、一体いくら必要なのか?
2019年時点のシミュレーションのおさらい
ではもう一度。
2019年の老後2000万円問題のモデルケースの老夫婦の前提を確認しましょう。
モデル世帯:夫65歳・妻60歳、無職世帯
毎月の収支:
- 支出:約 26.4万円/月
- 年金等の収入:約 21.0万円/月
- 不足額:約5.4万円/月
年金額の試算は…
- 夫が40年間会社員(平均的な給与水準)で厚生年金加入
- 妻は専業主婦(国民年金のみ)
- この場合の年金月額(夫婦合計):約21万円程度
※参考:厚労省「モデル年金額の例(令和元年)」
→ 国民年金(満額)=月65,000円前後
→ 厚生年金(夫)=月14〜15万円程度
年金はいくらもらえるの?
公的年金の受取金額は一人ひとり異なります。
年金定期便や年金ネット等を利用して、ご自身の公的年金額を把握しましょう!
今、冷静な目で見るとこんな違いがあります
- 専業主婦 → 今は共働きが多い
- 妻は国民年金 → 3号が廃止されそう
- 年金支給年齢 → 支給年齢引上げの可能性
- 持ち家&ローン完済 → 晩婚化や未婚が増えてローン残債ありや単身者も多い
- 医療費 75歳以上は1割負担 → 2割に変更か?
2000万円どころじゃなくなりそうなツッコミどころが満載…
では、実際どうなの??をいろんなパターンでやってみます!
夫婦とも正社員で共働き インフレ率2%の場合
2025年現在、35歳と30歳という夫婦が老後資金にいくら必要か、を試算してみます。
前提
- 夫婦ともに正社員(厚生年金フル加入)
- 老後の年金収入は 月28万円 と仮定(14万円×2名)
- 2025年現在夫婦2人の生活費は平均月30万円。
- よって、月2万円不足(2025年時点)を出発点に計算
- インフレ前提:
- 2019年→2025年で累積15%の物価上昇
- 2025年→2055年の間も年2%ずつ物価上昇
- 老後(2055年〜2085年)も年2%のインフレが継続
結果
仮にインフレ率2%で推移した場合…
❶ 2055年時点の生活費(インフレ反映)
月30万円×(1.02)30≒約553,408円
仮に、2%のインフレを続けた場合1ヶ月の生活費は55万円に!
これは贅沢ではなく、今と同じ生活にかかる費用です。
❷ 2055年時点の年金収入との差(不足額)
553,408円(支出)−280,000円(年金)≒約263,408円/月の不足
❸ 老後30年間の累積不足額(毎年2%インフレ)
30年間の総不足額≒約1億2,823万円
インフレ率2% 夫婦共働き正社員の場合の不足額
1億2,823万円(ただし、今の価値でいうと3400万円程度)

オワタ…
と、悲観したくなるのですが、ちょっとまって!!悲観するのはまだ早い!!
日本の公的年金(老齢基礎年金・厚生年金など)は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直し(改定)される仕組みがあります。実際には物価が3%上がると、年金額は1~2%程度上がる…みたいな感じです。なので、実際にはここまで深刻にはならないはず。
更に、こんなにインフレするなら、流石に給料も上がっているはず!!
そうです!上記の計算には、年金額アップと給料アップを計算に入っていないのでめちゃくちゃ厳しめに計算している結果です!!
そして、1億2,823万円ですが、今の貨幣の価値でいうと3,400万円です。(肩透かしのようでごめんなさい)
「昔はバナナ10円で高級品だったのよ!」みたいな昔話を聞いたことある人もいるかもしれませんが、1円の価値というの時代によって変化します。今、3400円を持っている人がそのまま現金で持ってたとしたら、価値はどんどん減っていき、いざ老後!というタイミングでは足りない!となるのでお気をつけ下さい。
今、老後に入る人は3400万円不足する
もし、「今から老後に入るよ~!無職になるよ~」という方の場合・・・
2019年からのインフレで物価は1.17倍、かつ、今後30年間のインフレ上昇年2%で計算すると
3400万円不足します。
夫婦とも正社員で共働きの場合 インフレ率1%の場合
1億円…と出たら、逆に非現実的だなぁと感じてしまうのが庶民の心。
もう少し現実的に考えられる
前提条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| インフレ率 | 年1% |
| 生活費の出発点 | 月30万円(2025年水準) |
| 年金額(合計) | 月28万円(共働き想定) |
| 老後期間 | 2055年〜2085年(30年間) |
結果
❶ 2055年時点の生活費(年1%インフレ)
30万円×(1.01)30≒約404,355円/月
❷ 年金との差(不足額)
404,355円−280,000円=約124,355円/月
❸ 老後30年間の累積不足額(2055年〜2085年)
総不足額≒約5,190万円
インフレ率1%でも約5,190円も不足する。

・・・(もはや言葉が出てこない)
● 2019年から2025年までの累積インフレ率(実績ベース)
日本の消費者物価指数(CPI)を見ると…
- 2020〜2021年はほぼ横ばいでしたが、
- 2022〜2024年のインフレは高水準でした。
2019年 → 2025年のインフレ率(累計)= 約17%
(出典:総務省CPIデータから試算)
もともとの2000万円不足という前提に、17%のインフレを適用すると
2000万円 × 1.17(= 17%増)= 2340万円
ここまでが「2025年時点の物価で換算した場合」の不足額です。
では、どう対応するのか!!サバイバル開始だ!!
NISAを活用する(年金と同額で)
NISAは現在は18歳以上から使えます。一人当たり最大1800万円まで、投資に対して発生した売却益や配当に対して、無税で受け取る事ができます。
前提条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月収(夫婦合計) | 60万円(各30万円 × 2人) |
| 年金保険料(自己負担) | 9.15%(厚生年金:労使折半) |
| 積立額(NISAに相当) | 月 54,900円(年金保険料と同額) |
| 運用利回り | 年4%(インデックス投資など想定) |
| 積立期間 | 30年(35歳〜65歳) |
仮に、54,900円(年金と同額)を夫婦でNISAに入れていった場合で計算してみます。
半分ずつで27,450円ずつ投資した…という試算です。
運用利回りは4%と低めで想定しています。
結果
65歳時点の資産総額(運用益含む):約3,762万円(夫婦合算で)
なお、1人あたり27,450円を30年間つみたて続けると
元本:約989万円
運用益:約892万円(4%複利で運用)
という結果になります。
NISA枠でいうと811万円分の枠が使っていない状況なのでちょっともったいないですね。
今度はこれを頑張って埋めるプランで考えてみましょうか…
NISAを活用する(なるべく早く埋める)
なるべく早く埋めたい!と言っても限度がありますよね。
年収800万円の平均的な夫婦(+子ども1人保育園児)の場合、貯蓄0円で投資に全振りした場合の最大で夫婦合算で15万円弱までなら投資することが可能…と、計算上は出ました。(全く保証はしないです)
年収800万円あっても、手取りになると600万円。50万円/月。
更に、住宅ローンや、食費、水道費などを支払っていくと、最大で15万円…
という感じです。もちろん貯金に回せる金額は0円!というスリリングな極端な生活を想定しています。
前提
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 月々の積立額 | 75,000円/人(夫婦で15万円) |
| 積立停止の条件 | 元本1,800万円に到達後ストップ |
| 積立年数(目安) | 約20年弱で到達、20年目以降は自由に使う |
| 1人あたりの最終資産額 | 約 4,039万円 |
| 夫婦2人分の合計資産 | 約 8,079万円 |
これだけやれば、インフレ率1%ならば乗り越えられる!
けど月15万円は…ハードすぎる…
iDeCoか企業DCを活用する!
iDeCoと企業型DCは自分で作る年金制度です。
■ iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)
- 国が用意した自分で作る年金制度です。
- 毎月一定額を自分で積み立てて運用し、60歳以降に受け取るしくみ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ほぼ全ての20歳以上60歳未満の人(会社員・公務員・自営業者など) |
| 拠出額 | 月5,000円〜上限(職業により異なる) |
| 税制メリット | ・掛金は全額所得控除 ・運用益も非課税 |
| 注意点 | 60歳まで引き出し不可。資金拘束あり |
■ 企業型DC(企業型確定拠出年金)
- 会社が加入してくれる、企業版の確定拠出年金。
- 掛金は会社が出すが、運用は本人が選ぶ。
- 最近では「マッチング拠出」といって、従業員が自分でも追加で積立できる制度も増えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 企業が制度を導入している場合、社員が対象 |
| 掛金 | 主に企業が拠出(+本人も拠出できる場合あり) |
| 税制メリット | ・掛金は非課税扱い ・運用益も非課税 |
| 注意点 | 60歳まで原則引き出し不可。転職時の移換が必要なことも |
iDeCoを知ろう!
iDeCoは60歳になるまで引き出す事ができません!それまではずーっと運用し続けることになります。
ですが、掛け金は所得控除になるなどメリットもあります!
詳しくは「iDeCoの基本を知ろう!」を御覧ください。
年収500万円の人が、毎月2.3万円を4%で30年間運用したらどうなる?
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 節税額(所得控除) | 約 165.6万円 |
| 積立額(元本) | 約 828万円 |
| 運用益 | 約 748万円 |
| 最終資産額 | 約 1,576万円 |
年収500万円の会社員が月23,000円(年間276,000円)をiDeCoで積み立てた場合
所得税率10%+住民税率10%と仮定すると→ 年間約55,200円の節税になります!
これを30年間続けると165.6万円の節税になります。
5万円の節税…と聞いても「案外少ない」となるかもしれませんが、30年の月日を続けると考えるとメリットとして大きい額になりますね。
また、運用益としても、大きいです。
iDeCoと企業DCの場合は、受取時の税金はNISAのように完全に非課税になっているわけではなく、退職金控除や公的年金等控除を利用する点は気をつけたほうが良いポイント。
というのも、退職金控除は変更されそうな控除の一つなので、もしかしたら受取時に税金が発生するように変更されてしまう可能性も残念ながらあります。受け取り方もチェックしましょう。
支出の見直しと生活防衛資金の確保とは?
① 支出の見直し:固定費の圧縮がカギ
老後の生活資金に不安があるとき、「支出を減らす」というのは極めて有効な戦略です。
■ なぜ固定費を見直すのか?
固定費(毎月必ずかかる支出)は、一度見直すだけで長期的に大きな効果を生みます。
退職後は収入が年金に限られるため、無駄な出費を減らして「老後の生活水準に合わせる」ことが重要です。
■ 代表的な固定費の例と見直しポイント
| 項目 | 見直しのヒント |
|---|---|
| 住宅ローン・家賃 | ローン完済の見込み・住み替え・賃貸⇄持家の見直し |
| 保険 | 医療保険・がん保険など、年齢に見合ったプランかを再検討 |
| 通信費 | 格安SIMへの乗り換え・ネットプランの再確認 |
| サブスク | 本当に必要なサービスか?不要なものは解約 |
| 車の維持費 | 自家用車を手放してカーシェアや公共交通に切替 |
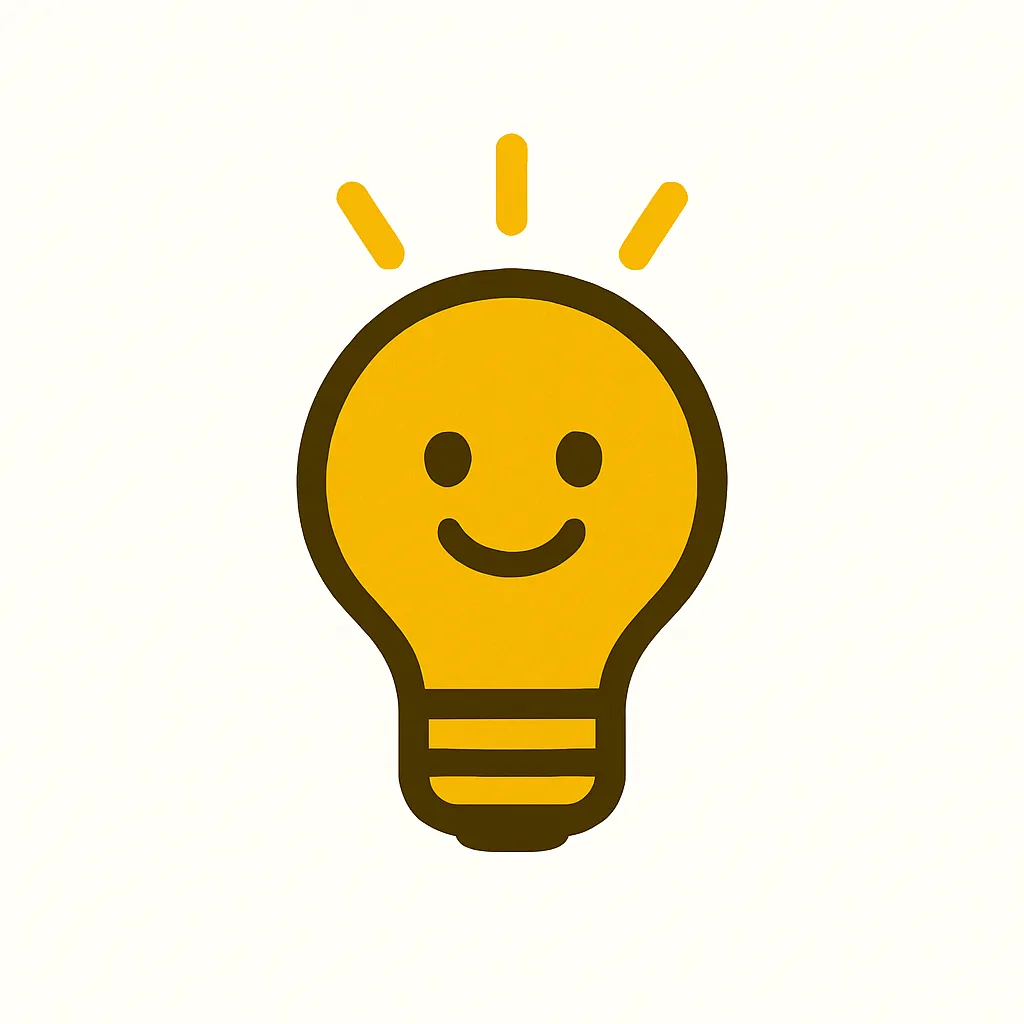
一度の見直しで「月3万円」減れば、年間36万円。老後30年で約1,000万円の節約効果に!
頑張る価値、ありますよ!!
スマホを格安SIMに変えると5000円/月の節約に。
サブスクも見直すと案外使っていないものも含まれてたりします。
固定費は一度見直すとずーっと効果が続くので効果絶大ですよ!
② 生活防衛資金の確保:6ヶ月分が目安
■ 生活防衛資金とは?
万一の事態(病気・ケガ・災害・失職など)に備える現金預金のことです。
投資とは別に確実に使える資金として、日々の生活を守るための「安全弁」です。
■ なぜ6ヶ月分なのか?
- 給与が止まったり、収入が不安定になったときでも生活を維持できる
- 投資資産が暴落したときにも、慌てて売らずに済む
- 失業保険の支給までに空白があることも多く、備えが必要
■ 金額の目安
たとえば月の生活費が25万円なら
25万円 × 6ヶ月 = 150万円!
これは投資せずにすぐに使える「普通預金口座」においておきましょう。
一般的には1年分くらいが望ましいと言われていますが、年齢や家族構成によって調整しましょう。
まとめ!!変化していく時代に、資産のあり方も変容を!
老後2000万円問題をインフレを考慮した結果を今回は試算してみました。
NISA口座は2025年3月末時点で約2,647万口座。
過去2年で約522万口座(+25%)増加しています。
今後も税制も社会も変わっていくでしょう。
現役世代の中でも若手からしたら、まだまだ変化の序章に過ぎないかもしれません。
これからも変わっていくであろう社会とルールに、敏感に反応出来るように。
自身の頭で論理的に考え、判断できるように、知識をつけておくことをおすすめします。
私自身も、変わっていくルールが難しい…と感じておりますが、頑張りますよ!!
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説
雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説 税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説
税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説 税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル
税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
免責事項
本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。
税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
本コラムの情報を用いて行う一切の行為およびその結果について、当サイトは責任を負いかねます。
実際の申告や手続き、具体的な判断が必要な場合は、国税庁・自治体等の公的情報をご確認のうえ、税理士などの専門家へご相談ください。


