相続税が初めて導入されたのは1905年(明治38年)。きっかけは、日露戦争でした。
この戦争は日本にとって初めての本格的な総力戦で、戦費は国家予算の7倍以上、約19億円(現在の価値で数十兆円)にも達しました。また、人類市場政府は外債を発行して英米から資金を借りましたが、それでも財政は限界。清国から巨額の賠償金を得た日清戦争とは違い、日露戦争では賠償金が1円も得られなかったのです。
その穴埋めとして導入されたのが、相続税でした。課税対象は「財産100万円以上の者」。当時の100万円というのは、いまの感覚で言えば庶民が一生かかっても手にできない金額です。消費者物価指数で換算すると約35億円、国家予算規模で見れば約600億円、地価水準で比べると1,000億円にも相当します。つまり、当時の相続税は現代でいえば数十億から数百億円の資産を持つ大財閥や大地主にだけかかる税金だったのです。相続税はもともと「庶民の税」ではなく、戦争のツケを富裕層に負担させるための富裕税として誕生しました。
なぜ賠償金がなかったのかというと、ロシアはまだヨーロッパ本国に大軍を温存しており、戦争を続ける余力があったためです。日本は旅順や日本海海戦で勝利したものの、兵力も財政も限界。これ以上戦えば国がもたない状況でした。そこで講和を仲介したのが、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領。日本の苦しい財政事情を見抜き、講和を急がせました。その結果、1905年のポーツマス条約で日本は南樺太の譲渡や満州・遼東半島の利権を得たものの、賠償金はゼロ。勝ったのにお金が入らないという、前代未聞の講和でした。
賠償金がないことを知った国民は激怒しました。「息子を戦場に送り出しても、国は何も得られないのか!」という怒りが噴出し、東京・日比谷公園で開かれた講和反対集会は暴徒化。新聞社や電車が襲撃され、官庁や警察署が焼き討ちされる「日比谷焼き討ち事件」へと発展しました。死者17人、負傷者数百人。戒厳令が敷かれ、首都は混乱に包まれました。世界的にも珍しい「戦勝国で暴動が起きる」という出来事であり、勝てば豊かになれると信じていた国民の期待が、現実によって裏切られた瞬間でした。
賠償金が得られなかった政府は、戦費返済と国債の償還のためにあらゆる税を引き上げます。酒税、煙草税、地租、そして新たに生まれたのが相続税でした。庶民からすれば「生きても税金、死んでも税金」。相続税はまさに「戦争のツケを払う象徴」として定着していきます。
その後、時代を経て相続税は富裕層だけでなく、一般家庭にも静かに広がっていきました。平成27年(2015年)の改正では基礎控除が大幅に縮小され、課税対象は全国で約8〜10%と、昭和のころの4〜5倍に増加。とくに都市部では自宅の土地だけで課税ラインを超えるケースが多く、もはや「相続税=庶民の税」と言っても過言ではありません。
たとえば、法定相続人が2人の場合の基礎控除は4,200万円。東京都や神奈川県では、自宅の土地だけで5,000万〜1億円を超えることも珍しくなく、預金や生命保険を含めると簡単に控除を上回ります。こうした家庭を救うのが「小規模宅地等の特例」で、居住用の土地(最大330㎡)は80%まで評価を下げられますが、同居や居住継続などの条件があり、すべての家庭が救われるわけではありません。
こうして、かつて財閥や地主を対象にした「死の税」は、いまや都市部の一般家庭にもかかる身近な税になりました。昭和のころには「相続税なんて一生関係ない」と思っていた家庭が、令和では「うちも対象になるの?」と心配する時代になったのです。
所得税でも相続税でも言えることですが、近年は【中間よりちょっと上の層】に厳しい税制が多いと感じております。
一方、海外では相続税のない国が増えています。オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、スウェーデン、ノルウェーなどはすでに相続税を廃止。アメリカやイギリスも高額控除があり、課税されるのはごく一部の富裕層だけです。これに対し、日本の最高税率は55%とOECD諸国の中でもトップクラス。日本では資産を守るために生前贈与や海外移住を検討する人が増える一方、相続税のない国の投資家やファンドが日本の土地や不動産を積極的に買い進めています。
北海道の広大な水源林、リゾート地の森林、自然豊かな離島、都市の商業ビルが次々と海外資本の手に渡り、「日本にあるけれど、日本のものではない土地」が増えているのが現状です。相続税のあり方が、いつの間にか国土の所有構造や富の流れにまで影響を及ぼしているのです。
税制は単にお金を集める仕組みではなく、国のかたちを映す鏡です。戦争のツケを払うために生まれた相続税。「お金もちから取れば良い」という発想は今もなお受け継がれていますが、その「お金持ち判定」は100年以上を経てどんどん下がっていき、今や年収1000万円前後でお金持ち判定をされます。アメリカで言うと1400万円以下は低所得だから奨学金免除などがあるくらいなのに。
もう一度いいますが、税制は単に財源を集める仕組みではなく、国のかたちを映す鏡です。生まれたばかりの赤子から中学生という子供にさえ扶養控除もなく、選挙の時だけ「子どもたちのために」というけれど、選挙が終わったら誰も言いません。その結果が少子化でしょう。そして、大人になり、一生懸命働き、稼ぎ、納税した残りのお金さえも、相続税として徴収され、支払えないから実家を売却→そして外国人の手に渡る…
一体、相続税はどの国のためにある税金なのでしょう?
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!? 暮らしと税2026年2月2日確定申告をできるだけ簡単に終わらせるデータ回収方法【サラリーマン編】
暮らしと税2026年2月2日確定申告をできるだけ簡単に終わらせるデータ回収方法【サラリーマン編】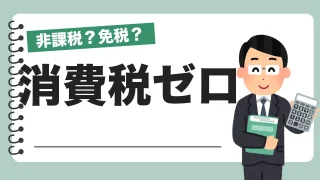 暮らしと税2026年1月28日【食料品の消費税ゼロ公約】免税と非課税で庶民に与える影響の違いを解説
暮らしと税2026年1月28日【食料品の消費税ゼロ公約】免税と非課税で庶民に与える影響の違いを解説 副業と確定申告2026年1月21日個人事業主の「節税しすぎ」「経費多すぎ」は賃貸・住宅ローン審査で詰む話
副業と確定申告2026年1月21日個人事業主の「節税しすぎ」「経費多すぎ」は賃貸・住宅ローン審査で詰む話

