
「働く」ってなんだろう
今、日本では「減税!」「減税!」という声が上がっています。
日本では「無税にしろ!」なんて言う人は一度も見たことはないのですが、世界は広いので、個人に税金がかかっていない国もごく少数ですが存在しています。
無税どころか、国から配当金のような形で収入もあった国をご存知でしょうか?
働かなくても生きていける。ただ、その土地・その家に生まれたという理由だけで生きていける。
と聞くと、羨ましいと感じたり、「んな楽園あるわけあるかい!!」とするどいツッコミが入ったり、「そんな馬鹿な!」と思ったり、色々な感情や思考が巡るのではないでしょうか?
私は色々この国を知って、日本に大した資源がなくてよかったなぁと感じましたよ。
ぜひ、皆さんも感じることがあったら、X等々を通じて教えて下さいませ!
第1章:ナウルという国を知っていますか?
南太平洋に浮かぶ小さな島国「ナウル共和国」。その名を聞いたことがある人は少ないかもしれません。面積はわずか約21平方キロメートル。東京・世田谷区の半分ほどの広さで、車で一周しても30分とかかりません。人口も1万人弱と、世界で3番目に人口の少ない独立国家です。
現在、大阪で行っている万博にもパビリオンを出しており、なんと大変人気!!そしてXでもナウル共和国政府観光局(公式)さんが大人気で頻繁にバズっています。せっかくなので、Googleマップでも御覧ください。
ち、ちいさい…
ナウルの税知識的に注目すべき点は、この国はかつて、「個人所得税がない国」、つまり“無税国家”として世界に知られていました。さらにその経済的な繁栄ぶりは、1970年代から1980年代にかけて、1人あたりGDPが世界トップクラスと称されるほどでした。税金を納める必要もなく、働かずとも国が国民を支え、生活に必要なインフラや医療・教育をほぼ無償で提供していたのです。
一見すれば、それは理想郷のように思えるかもしれません。働かずとも豊かに暮らせる。税金を納めずとも社会サービスは維持される。
――しかし、ナウルの繁栄は、ただ一つの資源「リン鉱石」に全面的に依存していたことを忘れてはなりません。
ナウルの国土の大部分は、かつて海鳥の排泄物が長い年月をかけて堆積した「グアノ(リン鉱石)」で構成されていました。このリン鉱石は、農業用の化学肥料の原料として極めて価値が高く、20世紀に入ると急速に国際的な需要が高まりました。ナウルはこの資源の輸出によって、莫大な富を得ることになります。
次章では、その「資源バブル」がナウルの社会にどのような影響をもたらしたのか、そして国民の労働観や税制がどう形成されていったのかを見ていきます。

第2章:働かなくても暮らせた国
ナウル人の“仕事観”はどう変わったのか…
ナウルの歴史をひも解くと、そこには劇的な“働き方の変化”が見えてきます。
もともとナウル人は、自らの手で生活の糧を得る、素朴で自律的な生活を営んでいました。それが、資源の発見とともに変容し、やがて“働かなくても暮らせる国”へと変貌していきます。
◉【Before】リン鉱石発見前:自給自足と部族社会(〜1900年)
ナウルの先住民社会は、12の部族で構成される伝統的な共同体でした。主な生活手段は沿岸漁業とココヤシ農業。食料や道具を家族や部族間で物々交換しながら暮らし、仕事は家族単位で分担されていました。
通貨はなく、労働とは“生きるために行う日常行為”。
働くことは自己や家族を支える当たり前の営みであり、富を蓄積するための手段ではありませんでした。
◉【After1】リン鉱石発見と植民地支配(1900年〜第一次・第二次世界大戦)
1900年、イギリス人探鉱者がリン鉱石(リン酸塩)を発見し、ナウルの運命は大きく変わります。
- 1900年:イギリス人アルバート・フラー・エリスがリン鉱石を発見。
- 1906年:ドイツ統治下で、イギリス資本のパシフィック・ファスフェート・カンパニー(PPC)が設立され、鉱業権を取得。
- 1920年:オーストラリア、ニュージーランド、イギリスによる国際リン鉱石会社(BPC)が設立。ナウルは事実上の採掘拠点に。
- 1914年〜1942年:第一次世界大戦を経て、オーストラリアが統治。鉱山経営を継続。
- 1942年〜1945年:日本軍が占領。多くのナウル人が強制移住や労働を強いられた。
この間、ナウル人は土地の所有権を持つ「地主」としての立場はなく、所有権は全くありませんでした。
豊富な資源があるナウルはその資源を求めて、何度となく戦火に見舞われ、虐殺や暴力が行われ、他島への強制移送され、劣悪な環境の中たくさんの方が亡くなり、人口は激減してしまいます。なんだか日本人としては大変忍びない気持ちになってしまいます。Xのナウル共和国政府観光局(公式)さんのポストには、大統領が不発弾を処理している画像もあり、一瞬目を伏せてしまいました。
第二次世界大戦が終わるまでの間、リン鉱石の恩恵はナウル人には薄かったようです。
◉【After2】独立と繁栄、そして“労働なき国家”へ(1968年〜1990年代)
- 1945年~1968年:オーストラリア、イギリス、ニュージーランドの三国による「信託統治」
- 1968年:ナウル共和国として独立。国民の多くが鉱山収益の配分を受けられるようになり、国家が生活を支える福祉国家モデルが本格化。
- 1970年代〜80年代:リン鉱石輸出によって国家は莫大な富を蓄積。国民1人あたりGDPは一時、世界トップクラスに。
- 医療・教育・公共サービスは無料、税金はゼロ、政府が住宅・生活を提供。多くの国民は労働を必要としなくなりました。
第二次世界大戦が終わると、再びオーストラリア等が信託統治することとなります。リン鉱石を掘り出すのは外国人労働者で、ナウル人は国から支援を受けて生きれる時代になりました。
◉ 【After2を深堀り!】生活費は国からの分配金!生活インフラも「国家持ち」
ナウルでは、土地の所有権はナウル人の一族(家系)に属しており、その土地がリン鉱石の採掘対象となった場合、一定のロイヤルティ(鉱業収入の一部)を受け取ることができました。ただし、収益の大部分はBPC(三国政府の鉱業会社)が持ち去り、ナウル人への支払いはごく一部だったそう…。それでも、農業や漁業の生産性が低い国において、この分配金が“事実上の生活費”となっていった家庭が多かったのです。
形式上は公務員や事務職に就いている者もいましたが、実態としては“ほとんど働いていない”状態。推定では、国民の6〜7割が実質的な無職だったと考えられます。
医療、学校、道路、水道などは統治当局(主にオーストラリア)が整備・提供。
税金は存在せず、国民が“負担する側”ではなく、“享受する側”に完全に回っていた。
経済活動は限られ、働かずに暮らす人が次第に当たり前になっていきました。
◉ 働かないことが“当たり前”になった社会
かつては「食べるために働く」ことが当たり前だった国でした。
ココナツの葉で編んだ網を使って漁業を行ったり、ココナツを育てて生活していた国でした。
ところが資源によって「配分を受け取るだけの社会」へと変わり、食べ物は外国からの輸入品に頼り、働くことの意味が失われていきました。
ナウルにおいて、「労働」は尊厳でも社会参加でもなく、無縁の概念になってしまったのです。
第3章:資源が尽きたとき、何が残ったのか?
ナウルにおける経済の根幹は、ただ一つの天然資源——リン鉱石に全面的に依存していました。その豊富な埋蔵量は、かつてこの島に集まった海鳥の排泄物が数百万年をかけて堆積し、極めて高品質なリン鉱床を形成していたためです。
しかし、無限の資源など存在しません。過剰な採掘と計画性のない運営により、1900年に発見されたリン鉱石は約90年後…1990年代には主要な鉱床はほとんど掘り尽くされ、2000年代初頭には輸出が事実上不可能な状態に陥りました。
こうしてナウルは、突如として国家財政の柱を失うこととなります。
推定ですが、ナウル人が働かなくても生きていけた期間は約50年間くらい。長いような短いような…。その50年間で、働かなくても生活が出来たナウル共和国の人々はどうなったのか!?
◉ 雇用の崩壊と「働き口のなさ」
もともと産業基盤が脆弱で、鉱業以外の主要産業が育っていなかったナウルでは、資源の枯渇と同時に雇用の受け皿も消滅しました。
多くの国民は就労経験が乏しく、高度な職業訓練や専門スキルを持つ者も限られていたため、国としての再建は極めて困難を極めました。労働観そのものが、「仕事をしないことが普通である」という価値観に染まっていたことも、社会の再始動を妨げる一因となったのです。
たった50年!!
おそらく、それまで何百年とご先祖さまたちは魚や木の実取ったりして生きてきたのに、たった50年でその文化が壊れた…
逆に言えば、50年はそれだけの年月ということです。
◉ 公共財政の急激な悪化と“無税制度”の限界
国家収入の9割以上をリン鉱石に依存していたナウルにとって、その喪失は致命的でした。
政府は苦し紛れに、国外の金融市場に多額の資産を運用しようとしましたが、投資の失敗や詐欺被害なども重なり、多くの財産を失いました。無税制度はもはや維持不能となったものの、税制の整備は進んでおらず、徴税のノウハウも不足していました。
◉ 外国頼みの経済運営へ
こうした財政破綻を背景に、ナウルはオーストラリアなど他国の援助に依存する道を選ばざるを得なくなりました。代表的なのが、オーストラリア政府との間で締結された難民収容所の設置契約です。
これは、オーストラリアに向かう第三国からの難民や庇護申請者をナウル国内に一時的に受け入れ、オーストラリアの財政支援で運営するというもので、ナウルの国家予算のかなりの部分を占めるまでになっています。もはや「独立国家」としての財政主権は極めて限定的と言わざるを得ません。
ぜひ、ナウル収容センターの口コミも御覧ください。日本人には刺激的すぎる?異文化な口コミが集まっています。どこからどこまでが冗談なのか、全く理解出来ないので、グローバルな方、解説をお願いします。
◉ 社会の荒廃と健康問題
かつての贅沢な暮らしを支えていたインフラは、資金不足によって次々と老朽化し、医療体制も崩壊。加えて、長年の運動不足と高カロリー食中心の生活が原因で、肥満率と糖尿病罹患率が世界最悪レベルにまで上昇しました。
本来ならば国民の健康を支えるはずの税と社会保険制度が存在しないため、医療機関で十分な治療を受けられず、重症患者は国外(主にオーストラリア)に搬送される事態となっています。
◉ ナウルが私たちに示す“無税国家”の現実
ナウルは、一時的には「無税」「高福祉」「高所得」を兼ね備えた夢のような国でした。しかしその繁栄は、限りある資源という土台の上に成り立ったものであり、持続可能性を欠いた“仮初の繁栄”に過ぎなかったのです。
資源が尽きたあと、何も残らなかった――。
それは、税制度を持たず、労働を軽視した国家が直面した当然の帰結であるとも言えるでしょう。
第4章:ナウルが教えてくれる「働くこと」と「納税すること」の意味
ナウルの歩みは、私たちに改めて「働くとは何か」「税金とは何のためにあるのか」という根源的な問いを投げかけます。
資源に恵まれた時代、ナウルでは生活のほとんどが国家によって支えられ、国民は働かずとも豊かに暮らすことができました。政府はリン鉱石の輸出収益を基に、医療・教育・インフラ・住宅を無償または極めて低額で提供し、個人から税金を徴収する必要すらありませんでした。
しかし、資源の枯渇とともにその体制は瓦解し、国民は経済的に困窮することになります。問題は、産業や就労環境が失われただけではなく、国民の多くが「働くこと」を生活の中心に据える意識を持ち合わせていなかった点にありました。
◉ 働くとは、何のためか?
資源が尽き、国家からの補助が途絶えたあと、多くの国民は働き口を求めました。しかし、教育水準やスキル不足、職業経験の乏しさが壁となり、ナウルの再建は困難を極めます。
この事例から見えてくるのは、「働く」という行為が単なる生活手段ではなく、社会に参加し、自己を高め、次の時代に備えるための基盤でもあるということです。
働くことは、収入を得る手段であると同時に、自らの能力を社会に還元する行為であり、個人の自立と社会の活力を支える礎です。国が富んでいるからといって、その力を使って働く文化を軽視すれば、社会の基盤は弱体化してしまうのです。
◉ 納税とは、“共同体”の支え手となること
同様に、ナウルが税制を整備しなかったことも、国家運営における重大な脆弱性をもたらしました。税収がなければ、政府は安定的に公共サービスを提供できません。無税国家は理想郷のように聞こえるかもしれませんが、裏を返せば「自国を支えるための仕組みがない」ということでもあるのです。
税金は、単なる負担ではなく、国家という“共同体”を支える会費のようなものです。社会インフラ、教育、医療、防衛、災害対応――それらは誰かの負担だけで成り立っているのではなく、私たち一人ひとりの納税によって成り立っています。
第5章:ナウルから学ぼう!
働き、学び、納める社会の持続性
ナウルの歩んできた歴史は、資源に恵まれ、国家が一時的にすべてを肩代わりできた“夢のような時代”を体現していました。
しかし、資源が尽きたとき、そこに残ったのは、産業も、技術も、安定した税制も育たなかった現実でした。
この物語は、私たちに対して“労働の意味”“学びの価値”“納税の意義”を問いかける、静かな警鐘でもあります。
◉ 働かなくても暮らせる時代は続かない
ナウルが繁栄していた頃、多くの国民は生活のために働く必要がなくなっていました。
政府が得たリン鉱石収益が、医療・教育・インフラを賄い、税も不要。いわば「国家に養われる社会」が成立していたのです。
けれど、こうした構造は資源という“他力”があることを前提とした、一時的な繁栄でした。
それが枯渇したとき、国には自立して再建する力が足りなかったのです。
働くことは、単なる金銭の獲得ではありません。
社会の一員として貢献し、仲間と連携し、他者の役に立つ行為です。
そしてその積み重ねこそが、社会を内側から支える「人の力」になります。
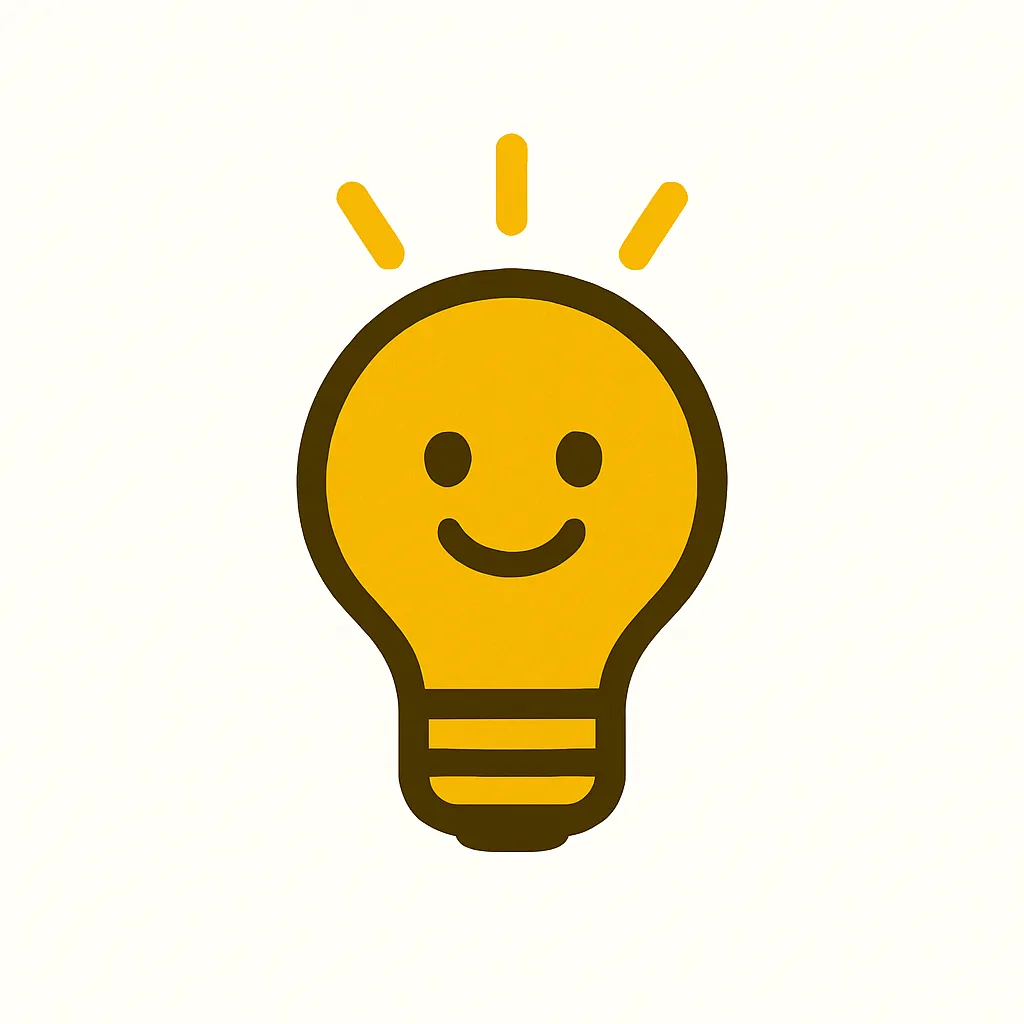
日本でも同様に、働くことはお金を得ることだけではない!と感じます。
◉ 学ばなければ、未来はつくれない
ナウルでは、長く外部からの富に依存する社会構造が続きました。
そのため、教育やスキルの習得が軽視され、人的資本が十分に育たなかったことが、資源枯渇後の再建を難しくした一因です。
大人も学ぼう!!
現代の社会では、変化に適応する力、学び続ける姿勢が不可欠です。
技術は進化し、経済は揺れ動き、何が“価値”とされるかも変わっていきます。
学びとは、社会における自己更新であり、未来への投資です。
学ぶことはどんなことでもいいと思います。
私自身、営業やりながら自宅でホームページの作り方を独学して、何個もホームページを作っては潰してを繰り返して、今のスタイルに落ち着いてから会社のホームページを自分でデザインするようになりました。それまでは外注で、ちょっとした修正にも数万円かかるのがとてもストレスでした。今自分でそれやれって言われたら5分で出来る仕事を5万円取って1ヶ月かかりましたからね…
勉強する、知識を得る、自ら手を挙げる…というのは責任は伴うけれども、自由に攻めの姿勢を取れるのは本当にありがたいし、
「会社以外の時間で、仕事のために時間を使うのならお金がほしい」とか
「プライベートの時間まで仕事を持ち込みたくない」とか、
生ぬるいことを言ってると、自己更新をしている人、未来へ投資している人と比較するとどうしても見劣りする人材になる…ということを覚悟したほうがいいと思います。
弊社では、会社が全額負担してどんな研修でも受けられる制度があります。けれど、それを実際に活用しているのは、なぜかほとんどいません。
ですが、別制度で、「税理士試験の科目合格出来たら資格学校の1科目会社負担します!」というのは毎年大人気コンテンツ(笑)
つまり「税理士になりたい勢」の勉強意識はあるものの、ほかのスタッフには勉強する意欲はあまりない…とも言えます。
以前勤めていた会社でも、資格試験の費用補助や教材支援があったのに、使っていた先輩はほとんどいなくて、申込み方法は誰もわかりませんでした。
制度があっても、学ぶ文化がなければ、動き出す人はごく一部。学ぶことを“浮いた行動”にしない環境づくりこそが、制度よりも先に必要なのかもしれません。
日本はもっと教育にお金をかけてもいいのではないか?
近年、中国の経済発展を支えているものの一つに、「教育への長期的な投資」があります。中国の教育支出はGDP比で10%近くに達し、大学や技術教育、研究開発に対して莫大な資金を投じてきました。その成果は、ハイテク分野での国際競争力の向上や、世界的企業の台頭として現れています。未来をつくるのは資源でも軍事でもなく、知識と人材です。
一方、日本の教育支出は1980年代にはGDP比5%近くあったものの、近年は3%台前半にとどまり、OECD加盟国の中でも下位に位置します。教育への予算が少なければ、家庭の負担が重くなり、学ぶ機会が格差となって現れます。学ばなければ、働き続ける力も、新しい価値を生む力も育ちません。
ナウルの事例が教えてくれるのは、「楽に暮らせる環境が人を怠け者にする」ということではなく、「学ばなくなった社会が未来を見失う」という厳しい真理です。教育は“今の生活”を豊かにするものではなく、“10年後の国のかたち”をつくる投資。税金の使い道として最も堅実で、かつリターンの大きい分野なのです。
◉ 納税は、社会への参加である
ナウルが財政危機に陥った最大の理由のひとつは、税制が整っていなかったことにあります。
豊かだった時代に「税金など要らない」として制度設計を怠り、いざ資源がなくなっても、社会を維持する財源が確保できなかったのです。
日本では、「税金は高い」と不満が語られることもありますが、それは道路、学校、病院、防災、年金、子育て支援など、多くの形で私たちの暮らしを支えています。
納税とは、ただの義務ではありません。
「この国の未来に、自分も責任を持つ」という意思表示でもあります。
また、言われるがまま納税をするだけではなく、税について勉強をしていくのも大事ですよ!
税についての知識は、我々【わかる税】を1日1つ読むだけで、一般人レベルで必要な税の知識は大体網羅出来るように……しておきます!!
◉ 私たちにできることは!?
ナウルを特異なケースとして遠ざけるのではなく、
「もし日本が農業などの一次産業や教育を軽視したら?」などと、日本や自分自身に問い直すことが大切です。
- 仕事に対する誇りを忘れないこと
- 知識を更新し続けること
- 税を通じて社会に関わる意識を持つこと
こうした積み重ねが、自立した個人と持続可能な社会をつくっていきます。
お金のために仕方なく働く…と思っていたとしても、もしかしたら、仕事のおかげで大事なものを守ってきているのかもしれません。
就職もいい、転職もいい、起業もいい!もちろん、専業主婦などで、社会の屋台骨として、地域活動や学校を支える人としてもいいと思います。
社会を支える側であること!という意識といいますか、こういうのは今まではっきりと考えたことなかったのですが、
それぞれがお互いに尊敬しあい、支えあえる社会にしていけたらいいなぁと感じます。
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説
雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説 税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説
税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説 税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル
税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
免責事項
本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。
税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
本コラムの情報を用いて行う一切の行為およびその結果について、当サイトは責任を負いかねます。
実際の申告や手続き、具体的な判断が必要な場合は、国税庁・自治体等の公的情報をご確認のうえ、税理士などの専門家へご相談ください。


