この記事にはプロモーションが含まれます
「保険金が出たら税金がかかるの?」
そう質問されることがありますが、答えは「場合による」です。
生命保険の税金は、契約者・被保険者・受取人の関係で大きく変わります。
同じ金額を受け取っても、「所得税」「相続税」「贈与税」など、まったく別の課税になることもあります。
1.まずは登場人物を整理しよう
生命保険には、主に3つの立場があります。
| 立場 | 役割 |
|---|---|
| 契約者 | 保険料を支払う人 |
| 被保険者 | 保障の対象になる人(亡くなったり病気になる人) |
| 受取人 | 保険金を受け取る人 |
この3人の組み合わせが、税金の種類を決めます。
2.生命保険の受け取り方で変わる課税の種類
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | 主な理由 |
|---|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 被保険者(夫)が亡くなり、妻が受取=相続扱い |
| 夫 | 妻 | 夫 | 贈与税 | 妻の死亡で夫が受取、保険料は夫が払っていない |
| 夫 | 夫 | 夫 | 一時所得(所得税) | 満期・解約で自分が受取る場合 |
| 夫 | 夫 | 子 | 贈与税 | 契約者≠受取人なので、贈与扱い |
| 自分 | 自分 | 自分 | 雑所得(所得税) | 個人年金など、継続的に受け取る場合 |
このように、「契約者と受取人が同じなら所得税」、「契約者と受取人が違うなら贈与税」、「亡くなった人が被保険者なら相続税」という整理が基本になります。
3.所得税の中でも「一時所得」と「雑所得」がある
一時所得とは?
- 一度きりの臨時的な収入
- 満期保険金、解約返戻金、懸賞金などが該当
- 計算式:(受取額 − 払込保険料 − 特別控除50万円)
総合課税に加えるタイミングで ×1/2 をしたうえで、×税率となります。 - 50万円以下なら課税されない優遇があります。
- 税率は総合課税なので、給与所得や公的年金などと合算して決定
- 一度きりの臨時的な収入なので、保険の場合は解約返戻金や満期保険金などが一時所得にあたります。
雑所得とは?
- 継続的または分類できない収入
- 個人年金、FX、仮想通貨の利益などが該当
- 計算式:(受取額 − 払込保険料+他の所得と合計)×税率
- 一時所得のような特別控除50万円や1/2課税はなし。
- 税率は総合課税なので、給与所得や公的年金などと合算して決定
- 保険を年金のように毎月コツコツ一定で受け取ると雑所得に区分されます
なので、雑所得と一時所得、どちらで保険金を受け取る方が得か…と聞かれると、50万円の特別控除と×1/2ができる観点から一時所得の方がお得といえます。
4.相続税と贈与税の違い
| 税金の種類 | 財産をもらう理由 | 主な例 | 非課税枠 |
|---|---|---|---|
| 相続税 | 人が亡くなったから | 死亡保険金、遺産、不動産など | 500万円 × 法定相続人 |
| 贈与税 | 生きている人からもらった | 親からの資金援助、生前贈与など | 年110万円まで非課税 |
つまり、亡くなった人からもらえば相続税、生きている人からもらえば贈与税。
生命保険でも、誰が保険料を払っていたかでこの線引きが変わるわけです。
5.まとめ:保険は「誰が払って誰が受け取るか」で課税が決まる
- 契約者と受取人が同じ → 所得税(一時所得・雑所得)
- 契約者と受取人が異なる(生きてる) → 贈与税
- 被保険者が亡くなり、相続人が受取人 → 相続税
そして、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人」という非課税枠があります。
これは相続税の中でも特に大きな優遇で、生命保険を相続税対策に活用する王道理由でもあります。
税理士からのひとこと
生命保険は、老後資金・教育資金・相続対策と万能に見えますが、
受取人の設定を誤ると、せっかくの節税効果が失われることがあります。
たとえば、契約者と受取人を別にしておくと、思わぬ贈与税が発生するケースも。
もし複数の保険を契約している場合は、受取人の設定を今一度確認しておくのがおすすめです。
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!? 暮らしと税2026年2月2日確定申告をできるだけ簡単に終わらせるデータ回収方法【サラリーマン編】
暮らしと税2026年2月2日確定申告をできるだけ簡単に終わらせるデータ回収方法【サラリーマン編】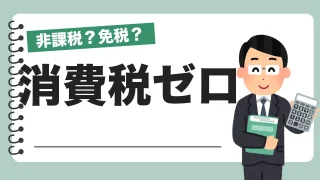 暮らしと税2026年1月28日【食料品の消費税ゼロ公約】免税と非課税で庶民に与える影響の違いを解説
暮らしと税2026年1月28日【食料品の消費税ゼロ公約】免税と非課税で庶民に与える影響の違いを解説 副業と確定申告2026年1月21日個人事業主の「節税しすぎ」「経費多すぎ」は賃貸・住宅ローン審査で詰む話
副業と確定申告2026年1月21日個人事業主の「節税しすぎ」「経費多すぎ」は賃貸・住宅ローン審査で詰む話


