
皆さん、こんにちは。
先日「トランプ大統領と関税15%で決着!」というニュースが飛び込んできました。
「消費税を守る!」と言ったのを守ったのですが、消費税は知ってても、関税に詳しい人って輸出入をしてない人にとってはちょっとわかりにくいものではないでしょうか?
私もわからなかったので調べてみました!!
第1章 そもそも「関税」ってなに?
ニュースで「関税が上がる」「関税をかける」と聞くと、
なんとなく“国同士のけんか”とか“物が高くなる”というイメージがあるかもしれません。
でもそもそも、関税ってどんなしくみ?なぜあるの?
そんな疑問から整理してみましょう。
■ 関税とは、外国からの「物の入国料」のようなもの
関税とは、外国から商品を輸入するときに、その品物にかけられる税金のことです。
たとえば、アメリカから日本に牛肉を輸入するとき。
1kg 1,000円の牛肉に25%の関税がかかると…
実際の仕入れ価格は1,250円になります。
つまり、関税があると外国製品は高くなりやすいんですね。
■ なんでそんな税金をかけるの?
関税には3つの大きな目的があります
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| ① 国内産業を守る | 安い外国製品が大量に入ると、国内の農家や工場が潰れてしまう恐れがあるため、価格を上げて“ハードル”を作る |
| ② 税収を得る | 国にとって関税は大事な収入源。たとえば明治時代の日本では、国の収入の半分以上が関税でした |
| ③ 外交カードに使う | 「関税かけるぞ」は立派な交渉手段。圧力として使うこともあれば、手を緩める代わりに譲歩を引き出すこともあります |
この記事を読んで頂くと今回のトランプ大統領も、外交カードに関税を巧みに使っていることがよーくわかります。
■ 関税がかかるとどうなる?
- 国内の製品が売れやすくなる
→ たとえば、外国の安い米が高くなることで、国内の米農家が守られます - 消費者はちょっと損をするかも
→ 関税のぶん、輸入商品が高くなります - 相手国との関係がこじれることも
→ 相手から「報復関税」をかけられて、輸出企業が苦しくなるケースもあります
だいぶ前ですが、トランプ大統領が「関税を上げる!」と宣言をした際、多くの国がアメリカに交渉を持ちかけましたが、一方で報復関税をかけた国もありました。結果的に、交渉をしようとした国に関しては関税を下げると発表されたり、関税とは戦争だ…と密かに感じました。
■ 関税がないとどうなる?
一方で、自由貿易(=関税ゼロ)にすると:
- 安い輸入商品が入ってきて、消費者にはうれしい
- でも国内の産業は厳しくなる
- 雇用が失われたり、食料自給率が下がったりする恐れも…
つまり、関税は「守るための盾」であり、「駆け引きの武器」でもあるんです。
■ 日本は農業で関税をたくさん使っている
日本では特に農業分野で関税を重視しています。
たとえば米には、
- 1kgあたり約341円、つまり「実質700%以上」の関税がかかっていた
- 外国産米がほとんど流通しないようにしている
これは、日本の田んぼや農村を守るための“防波堤”とも言える関税です。
つまり関税とは?
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 関税とは? | 輸入品にかかる「入国料」のような税金 |
| なぜある? | 国内産業を守る・国の税収・外交交渉のため |
| 影響は? | 輸出入商品は高くなるが、国の安全・雇用を守れる |
| 日本の特徴 | 特に農業では“超高い関税”で国内を保護してきた |
第2章 アメリカが「15%関税」をかける理由とは?
2025年7月、アメリカ(トランプ大統領)はこう発表しました。
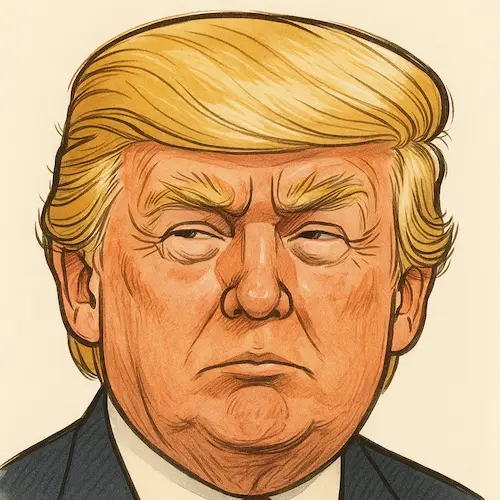
8月1日から、日本などの国からの輸入品に15%の関税をかける!これは“新しい世界標準”だ!
この15%という数字、ただの思いつきではなく、実はアメリカの“戦略的なメッセージ”が詰まっています。
■ 元は25%!? 日本にとっては“引き下げ”だった
実は当初、アメリカは日本製の自動車や部品などに「25%の関税」をかけようとしていました。
これはかなりの高関税で、日本の輸出企業にとっては大打撃になりかねません。
▼ ところが…
- 日本がアメリカに5500億ドル(約80兆円)規模の投資を約束
- その見返りとして「じゃあ、関税は25%じゃなくて15%にしてやる」とアメリカが発表
つまり、“脅し”→“譲歩”のような形で、関税が少し緩和されたという流れです。
■ なぜ15%?中途半端な数字の意味
15%というのは実は「ちょうどいい数字」なんです。
| 数字 | 意味 |
|---|---|
| 10%以下 | 弱すぎてアメリカの産業は守れないし、交渉力も示せない |
| 25%以上 | 高すぎて相手国(日本やEU)との対立を生む |
| 15% | 「関税かけた感」はありつつも、実害を少し抑えられるライン |
要するに、
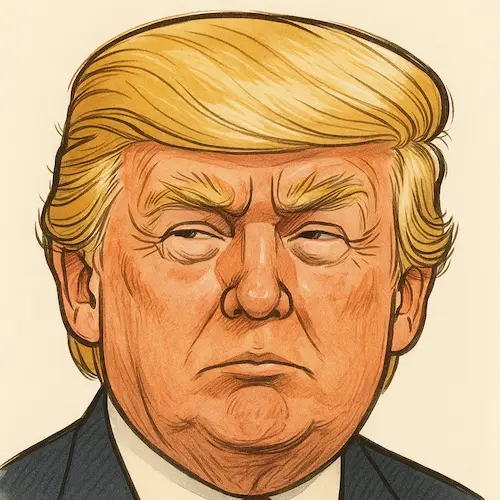
ほどほどに圧力をかけつつ、話し合いの余地も残しとこ
という、トランプ流の“揺さぶり関税”です。
■ なぜ関税を使いたがるのか?トランプ流の本音
トランプ大統領が関税を使いたがる理由はシンプルで、こうです。
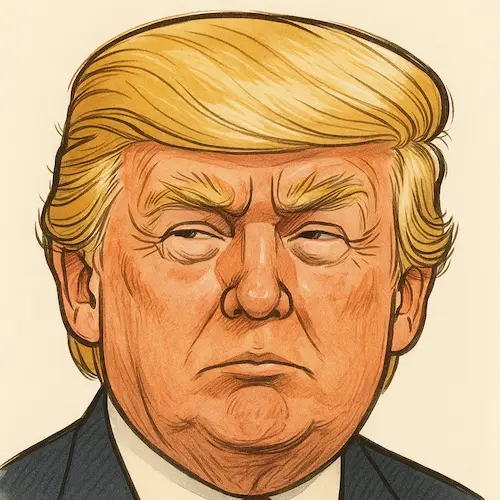
アメリカにとって不公平なら、関税で対抗する。嫌なら投資しろ。買え。雇用しろ
つまり、関税は「取引の材料」であり、「実利を引き出す手段」なんです。
たとえば、今回のように
- 「日本に関税かけるぞ」と言う
- 日本が投資や輸入枠拡大で応じる
- 「なら少し関税を引いてやる」
- アメリカに投資が集まり、トランプ氏は「勝った」とアピール
という「一発交渉型」のやり方が特徴です。
■ 日本だけじゃない、他国にも15%要求中
実はこの“15%”は、日本だけの話ではありません。
- トランプ氏は「15%関税を“世界標準”にする」と言っています
- EUや韓国、カナダ、台湾などの主要貿易相手国にも同様の提案・圧力をかけている状況です
つまり、今回の日本との合意は他国との交渉のたたき台でもあり、世界中が「うちも15%か?」と注視しています。
■ 日本はそれにどう応じたのか?
日本は表向きはこう言っています

自由で公正な貿易を重視しており、関税の一律引き上げには慎重な立場
う~ん…ちょっとわかりにくいけど
実際には高関税を回避するために、経済的譲歩(=投資や農産物の輸入緩和)で合意に応じました。
つまり――
「強くは反対しないけど、手を打って妥協した」というのが実態に近いのです。
では、何を妥協したのか?詳細を見ていきましょう!
第3章 80兆円投資って誰が出すの?「支払う」って本当?
前章で見たように、アメリカの「15%関税」という圧力に対し、日本は「それを避けたい」という立場から、いくつかの“譲歩”をして合意を取りつけました。
その中でも、ひときわ注目を集めたのが――

「5500億ドル(約80兆円)の対米投資ですって!?
ほぼ毎週のように「日本政府、●●に◎◎億円資金提供」みたいなニュースが流れるので、また日本政府が国庫から「日本がうん十兆円を支払う!?」といった誤解を招く表現も見られましたが、冷静に中身を見ていきましょう。
■ 金額は本当に「80兆円」なの?
今回、日本が合意した投資総額は5500億ドル(約80兆円)規模。
これは、企業の出資、工場建設、技術提携、エネルギー契約、金融融資など、さまざまな形で「アメリカ経済に貢献する」という名目の民間投資です。
しかも!!アメリカならどこでも投資していいよ~♪というものではなく、
アメリカの指示で、アメリカの指示した場所に、投資することを指示されている上、投資から得られる利益は90%はアメリカのもの!
■ 「投資」ってどういうこと?「支払う」とは違うの?
ここがとても大事なポイントです。
これは、政府が「お金をあげる」のではなく、
- トヨタ、ソニー、三菱商事、日立などの民間企業
- 日本政策投資銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)といった政府系金融機関
が、アメリカの事業やプロジェクトに投資するというものです。
つまり、アメリカに工場作って、アメリカ人雇ったり、経済活性化してね!ということです。
支払うと違うのは、その民間企業自体も、アメリカに投資し、営業することで、利益を得ることが出来る点です。
※ホワイトハウスから得られた文書で、アメリカの指示で、アメリカの言う通りに投資する…と書かれているため、この民間企業の戦略でアメリカに投資…というわけでもない上、利益の90%はアメリカのものになります。
■ なぜそんな投資をアメリカにするの?
これが今回の合意の“バーター(交換条件)”の本質です。
アメリカ:「関税かけるぞ」
日本 :「やめてほしい。じゃあ、投資するから」
アメリカ:「OK、じゃあ15%で手を打とう」
という“取引”が行われたというわけです。
日本の輸出産業(特に自動車)にとって、関税が25%に跳ね上がるのは致命的。
その回避手段として、「アメリカで雇用と成長に貢献する=関税を抑えてもらう」という構図です。
■ 民間企業に投資を促す?どうやって??
ですが、日本政府がお金を出すわけではなく、日本の企業が、アメリカに投資するように促すというわけです。
アメリカに投資したくてウズウズしていた企業ばかりなら良いのですが、そうでもない企業ばかりだったら約束を守れなくなってしまいます。
そのため、日本政府も民間企業に対し、アメリカに投資するように圧力や補助を出すかと思われます。
① 政策金融での“後押し”
- 政府系の日本政策投資銀行(JBIC)、国際協力銀行、NEXI(日本貿易保険)などを通じて
- 低金利で融資を提供
- 海外投資に対する保証(たとえばアメリカの政治リスク、為替リスク)
- 投資先インフラへの優先アクセス(港・資源・政府調達など)
企業にとっては「やるリスクが小さくなる=やらない理由がなくなる」構造です。
※これ、投資がうまくいかなくて、万が一、焦げ付いてしまったら、国民負担です…
② 経済産業省・外務省などによる“調整要請”
- 非公式に、「この分野に投資案件ありませんか?」「日米関係の安定のためにも、積極的な対応を」といった要請が入ります。
- 業界団体や大手企業幹部との意見交換会、会議を通じて“空気をつくる”ことも。
これはまさに「お上の意向」を“汲む”構図です。
③ 補助金や制度優遇による“実利的誘導”
- 海外事業の環境整備費、研究開発支援金、現地拠点整備補助などの名目で公的資金を投入
- 海外向け輸出案件や製造拠点への税制優遇措置
- 経済連携協定(EPA)や通商枠組みにおける便宜供与
これにより、「どうせ投資するなら、今が一番オトク」という状況を作り出すのだろうなぁと予想されます。
■ 投資内容って何に向かってるの?
ニュースや政府資料によると、主な投資分野は…
- エネルギー(LNG、再エネ)
- 半導体・AI・データセンター
- 医薬品・バイオ・ヘルスケア
- 港湾・輸送・鉱物資源・物流網
こうした分野は、アメリカが強化を狙っている戦略産業でもあり、日本の技術や資金を呼び込む形で“雇用と投資”を得ようとしています。特に、アラスカのLNG(液化天然ガス)の開発は採算が取れなさそう…と言われているものにも、日本が投資をしないといけなくなるかも?
■ ちなみにトランプ大統領は…
トランプ大統領はこの投資について、
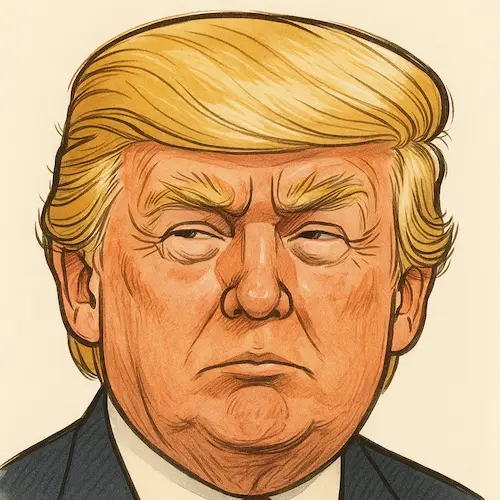
アメリカが90%の利益を得るディールだ!
これまでにない最高の取引だ!
と強調していますが、これはあくまで政治的アピール。
実際にどのような配分になるかは不透明であり、日本側も「利益回収できる案件」であることが前提です。
第4章 自動車産業への影響は?得したのは誰?
アメリカとの関税交渉で、最も注目されたのが自動車産業です。
トヨタ、ホンダ、マツダ、日産、スバル…いずれもアメリカ市場での売上が非常に大きい企業ばかり。
彼らにとって、関税が25%になるか15%で済むかは、まさに“生死を分ける”ほどの重要問題だったのです。
■ 自動車への関税、どうなる予定だった?
トランプ大統領は当初・・・
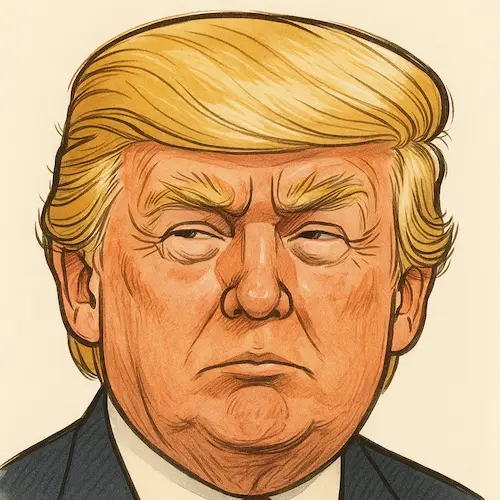
海外製の自動車には25%の関税をかける!アメリカの雇用と工場を守るためだ!
と強硬姿勢を見せていました。
これは「トヨタの車1台が500万円でも、アメリカでは625万円になる」ようなインパクトで、日本車メーカーにとっては悪夢のような話です。
■ 今回の合意でどうなった?
日本側が80兆円の投資などを提示した結果――
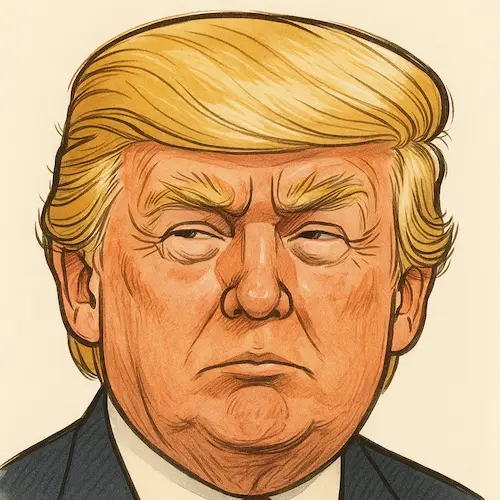
じゃあ、関税15%で勘弁してやる
という形に。
つまり、自動車業界にとっては、
- 最悪の「25%」は避けられた
- ただし、今までほぼゼロに近かった関税が「15%に上がる」のは事実
…という 助かったけど痛い状況です。
■ 日本の自動車メーカーはどう反応した?
短期的には「大崩れを避けた」として、株価は一部上昇しました。
しかし業界全体としては、慎重なスタンスです。
「15%はやはり大きな負担。現地生産の拡大で対応するしかない」
「企業努力では吸収しきれない価格上昇になる恐れがある」
という声も上がっており、根本的な解決ではないと認識されています。
■ アメリカの自動車メーカーはどう見てる?
トランプ政権は「アメリカ車を守るため」と言っていますが、実は国内メーカー(GM、フォードなど)から不満の声も出ています。
その理由は:
- 日本車は既に現地生産比率が高い(関税の影響が限定的)
- アメリカ車は輸出比率が低く、日本市場では売れていない
- 一方でアメリカ企業は依然として鉄鋼・アルミに50%の関税をかけられており、コスト増の不公平感が残っている
つまり、日本だけ得をしているように見えるという国内批判も起きているのです。
実際、アメリカ車を乗ってる人…ご近所を見ても、会社の近くで見ても、あんまり走っていないんですよね…
何ていうか、大きくて日本の道は走りにくそうなイメージ?燃費悪いイメージ?もあったりして…
第5章 そして見逃せないのが農業 ― 米や豚肉は大丈夫?
関税の話題というと、自動車や鉄鋼のような「工業製品」が注目されがちです。
しかし、日本にとって関税でもっとも神経質になるのが――そう、農業です。
特にお米や豚肉、乳製品などは、「外国の安い農産物から守る」ために長年かけて高い関税で防御してきた“聖域”ともいえる分野。
今回のアメリカとの合意で、この農業分野にどんな影響があるのか、しっかり見ていきましょう。
■ アメリカは以前から「米をもっと輸入しろー」と言っていた
アメリカの農業団体(特に米生産者連合)は、以前からこう主張してきました。

日本はコメに700%以上の関税をかけて、アメリカ産米を締め出している。これは不公平だ!
実際、日本の米には1kgあたり341円の関税がかかっており、輸入をほぼ不可能にしている状態。
もちろん、この高い関税は日本の米農家を守るための政策。
これは“日本の米農家を守る最後の砦”とも言える制度です。
■ 今回の合意でどうなったの?
2025年7月の合意では、農業に関しては表向きこう発表されました
「農業分野では譲歩していない。関税は維持している」
…が、その一方で、実質的な“譲歩”とも言える中身が含まれていました。
■ 実際にはこんなことが決まりました
アメリカ産米の輸入を“枠内で拡大”
- WTO(世界貿易期間=世界の国々が集まって、貿易のルールを決める場所)で認められている「無税輸入枠(最低輸入枠=77万トン)」の中で、アメリカ産の比率を75%増やす。それも即座に!!
- つまり、関税は維持されているが、“実質アメリカ米の輸入が増える”
- だけど、主食用のお米には回らない
トウモロコシや大豆などの輸入量も増える見通し
- 日本は「米国農産物8ビリオンドル相当の輸入拡大」を約束
- これにより飼料用トウモロコシ(=畜産業)にも波及する可能性
食品・バイオ燃料分野での米国産品の採用促進
- バイオエタノール(トウモロコシ由来)を使う燃料混合比率の緩和が交渉対象に
- 国産の米粉や麦由来エネルギーとの競合懸念
■ 日本の農家にとって、どこが“ピンチ”なのか?
① 米の価格がじわじわ下がるおそれ
- 米の「最低輸入枠」は、学校給食・外食・加工用などの用途に使われることが多いです。
→国産米の需要が落ちてしまい、価格が下る。 - 国産米の価格が抑えられ、農家の収入が減るリスク→日本の米農家減少のリスク
また、地域経済にも打撃を与えますし、耕作放棄地が増えてしまいます - 農家への補助金が減る可能性あり。ただでさえ、米が安くて米農家はやめたいと言い出すくらいなのに!?
② 「農産物は聖域」が崩れた事実
- 表向きは「譲歩してない」とされているが、輸入枠の拡大=事実上の一歩後退
- 一度緩めた枠組みは、次回交渉時に“基準”として使われてしまう
- 次の聖域も侵攻(?)される可能性あり
③ 輸入依存が進み、食料安全保障に懸念
- 日本はもともとカロリーベースで食料自給率37%(2023年)
- さらに輸入依存が進めば、災害・戦争・通商摩擦の際に国民の食料が確保できなくなるリスク
戦争をしなくても、食料を売ってくれる国がなくなったら餓死してしまう…
そんな国でいいのか!?
④【地域経済的ピンチ】“農業=経済”な地域が崩れる
地方では、農業がただの産業ではなく、
- 地域の雇用(農協、農業法人、物流など含めた複合経済)
- 祭りや神事、景観の維持
- 若手の就農支援や定住政策の柱
など、地域社会そのものを支える土台になっています。
■ 農業団体や保守政治家の反応は?
- 自民党内では農林族議員を中心に「農業を取引材料にするな」という声が出ています
- JAグループなども「関税は維持されたとはいえ、実質的な譲歩だ」と警戒感を示しています
ただし、農業政策は選挙と密接に関わるため、政府としても“あからさまな譲歩”は避けつつ、“実務的な調整”で帳尻を合わせている、という構図です。
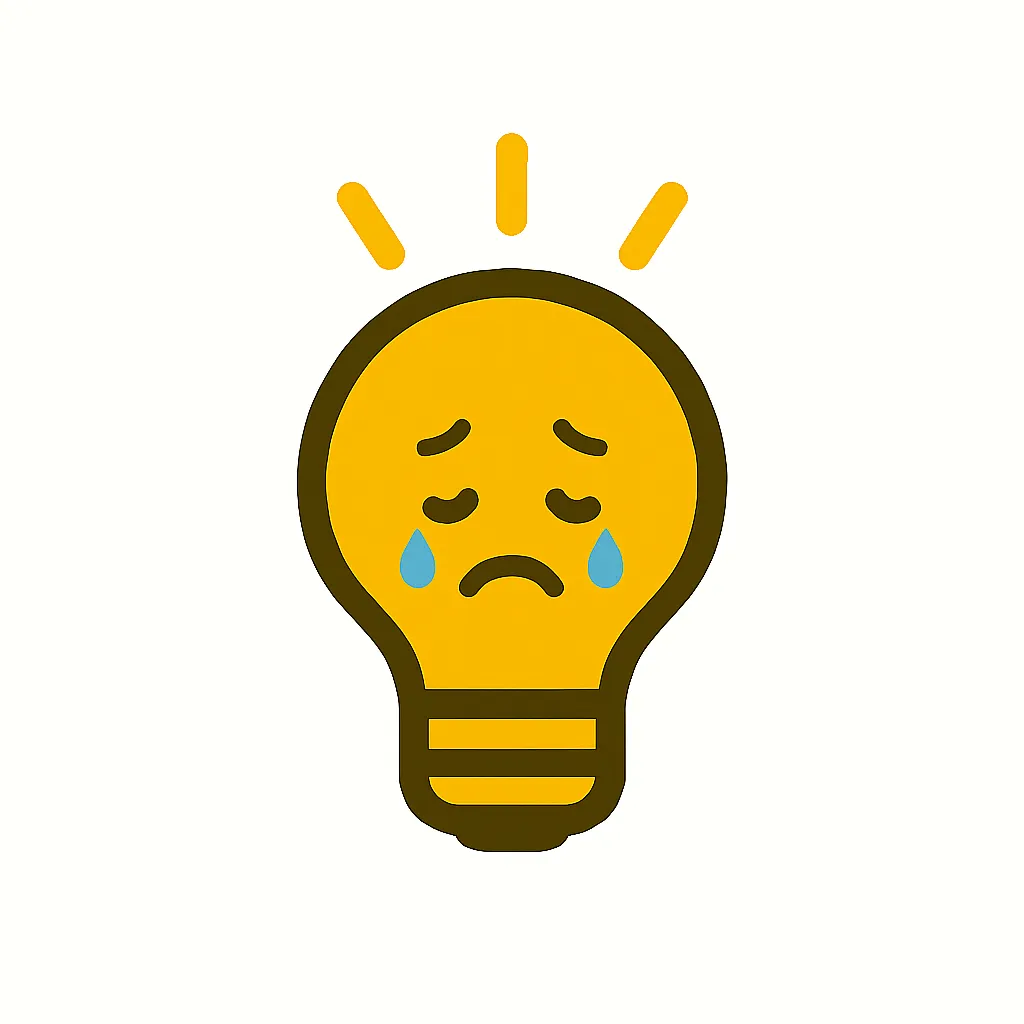
自国の主食である「米」を自力で作れなくなるようでは、外交的にめちゃくちゃ弱い国なります。本当にそれでいいのか?米の価格が下がればそれでいい…とは思わない日本人も多いはず!
第7章 この影響、私達の生活にどう関係する?
ニュースでは「日米関税交渉合意」「80兆円投資」と難しい言葉が並んでいますが、
結局、私たちの生活にどんな影響があるの?と感じる方も多いでしょう。
ここでは、身近な“物価・雇用・食卓”という3つの切り口から、この合意が私たちにどう関わってくるのかを見ていきます。
🏭 1. 自動車産業と雇用:あなたの周りの仕事は大丈夫?
自動車業界の打撃が「15%で済んだ」ことの意味
- トヨタ・ホンダ・マツダなど日本の自動車メーカーは、輸出の多くをアメリカ向けに頼っています。
- もし関税が25%になっていたら、日本からの車の価格が一気に上がり、売れなくなる → 生産調整 → 雇用にも影響が出ていたでしょう。
自動車関連の地域(愛知・静岡・九州など)は…
- 地元の製造業や下請け、中小企業まで含めて「とりあえず一安心」
- 今後もEVや部品の現地化要求は続くが、「今回の合意で時間稼ぎができた」とも言えます
雇用不安の“即時爆発”は避けられたが、根本の構造リスクは残ったまま
2. 食卓と物価:安くなるの?高くなるの?
アメリカ産農産物が増えるとどうなる?
- 米・トウモロコシ・大豆などが増えれば、加工食品・外食産業では原料コストが下がる可能性もあります。
- しかし、実際には円安や輸送コスト、価格調整の仕組みもあり、目に見えて「安くなる!」とは言いにくい状況です。
一方で心配なのは国産品の“影響”
- 安い外国産が入ってくることで、国産米の価格がじわじわ下がる
- 「高くても安心だから国産を選びたい」層にとっては、選択肢が減っていくリスクも
- 特に地方の産直市場や小規模農家の米は、流通が減り、消えていく可能性も
食卓にはすぐには表れないが、10年後の“お米売り場”が変わっているかもしれない…
「国産派」の皆様は、農家を応援しましょう!
💵 3. 財政・税金・未来:あなたの“財布”にも影響が?
80兆円投資の“財源”はどこから?
- これは政府が全部税金で出すわけではありません。
- 多くは民間企業による投資ですが、政府系金融(JBICなど)が保証や融資を出すため、一定の国費=税金も関与します
さらに政府の“外交パッケージ”には…
- 今後、輸入関税収入が減る(無税枠拡大で)可能性あり
- 代わりに国内農業や産業への「補助金」が増えれば、それも税金負担につながります
➡ 間接的ですが、数年スパンで「政府支出の見直し=増税圧力」に変わる恐れもあり。
どのように、今後日本の農業を守っていくか…は我々の食卓にも大きな影響があるかと思います。
まとめ:見えてきた“譲歩の代償”と日本のこれから・・・
2025年7月、トランプ政権下のアメリカが日本に対して「15%の関税をかける」と圧力をかけたことに端を発する今回の交渉劇。
表向きは「合意に達した」「関税は上がらなかった」とされていますが、その裏には――
トランプ関税15%のまとめ
📌 80兆円の対米投資
📌 アメリカ農産物の輸入拡大(特に米)
📌 農業の“聖域”崩しの序章
といった、大きな“代償”がセットになっていました。
そして、今まで関税がかかっていなかった輸出も、15%の関税がかかることになります。自動車産業以外でも輸出している企業は今まで関税がかからなかったところから15%かかるようになる事業者もいます。
また要注意ポイントもあります。
なんと、当記事を書いている最中にも速報が!!
石破総理との党首会談を行いました。
— 玉木雄一郎(国民民主党) (@tamakiyuichiro) July 25, 2025
結論から言うと、以前私が申し上げた日米関税交渉の結果を「評価する」とのコメントは撤回します。
共同文書もなく内容が全くピン留めされていません。驚きました。
15%の関税率もいつ25%に戻るか分からない状態です。
詳細はたまきチャンネルで解説します。 pic.twitter.com/jelI0D80zB
つまり、コレは…
決まってない!?
いや、定まってない?
っていうか、石破さんは文書を作る気もなかったみたいし、トランプ大統領の気分次第ではドカーンと手のひら返しもまだまだあり得るのかも…
世界はトランプの手のひらの上で踊らされている…
また情報あったら当記事を書き換えます。
投稿者プロフィール

-
税理士法人、行政書士法人、社労士事務所などのグループです。
税制は複雑化していく一方で、税理士を必要としない人々の税に関する知識は更新されていない…と感じ、より多くの人が正しい税知識を得て、よりよい生活をしてもらえたらいいなぁと思って開設したサイトです。専門用語には注釈をつけたり、いつも払っているだけの税金のその先も知ってもらえたら嬉しいです。
最新の投稿
 雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説
雑談2026年2月19日AIで申告できるのに税理士は必要?残る仕事を解説 税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説
税理士事務所の内部2026年2月18日税理士と相談って具体的に何ができる?税理士が解説 税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル
税理士事務所の内部2026年2月17日税理士事務所の繁忙期っていつ?残業時間は?働き方のリアル 雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
雑談2026年2月3日消費税12%の衝撃!選挙の投票先はどうする!?
免責事項
本コラムは、税金に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な状況に対する助言(税務申告・節税判断・手続きの代行等)を行うものではありません。
税制や運用は改正・変更されることがあり、本コラムの内容は執筆時点の情報に基づいています。可能な限り正確な情報を掲載するよう努めていますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
本コラムの情報を用いて行う一切の行為およびその結果について、当サイトは責任を負いかねます。
実際の申告や手続き、具体的な判断が必要な場合は、国税庁・自治体等の公的情報をご確認のうえ、税理士などの専門家へご相談ください。


